
お話をしてくれた方

山中 恭二さん
兼松エンジニアリング株式会社
開発部
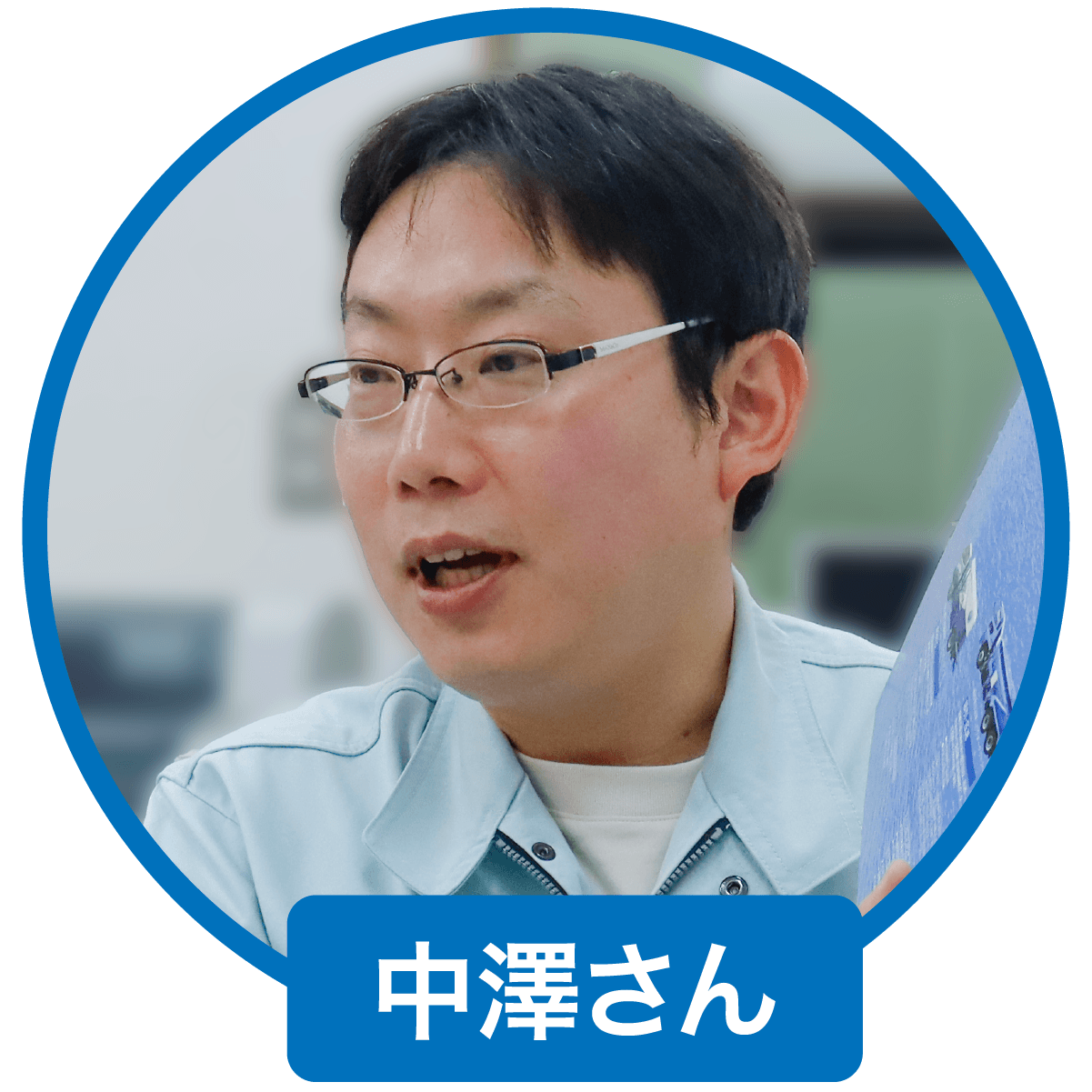
中澤 光宏さん
兼松エンジニアリング株式会社
開発部
道路の清掃や工場の廃棄物回収などに活躍する「環境整備機器」を手がける兼松エンジニアリング株式会社。そんな同社が、これまで廃棄されていた資源を有効活用し、新たな価値を生み出す技術開発に取り組んでいることをご存じでしょうか?
今回は、脱炭素社会の実現に向けた挑戦について、兼松エンジニアリング株式会社の開発部・山中恭二さんと中澤光宏さんにお話を伺いました。

未利用だった資源を生かして地球にも地域にも貢献


- 兼松エンジニアリング株式会社さんはどういった事業をおこなっている会社ですか?
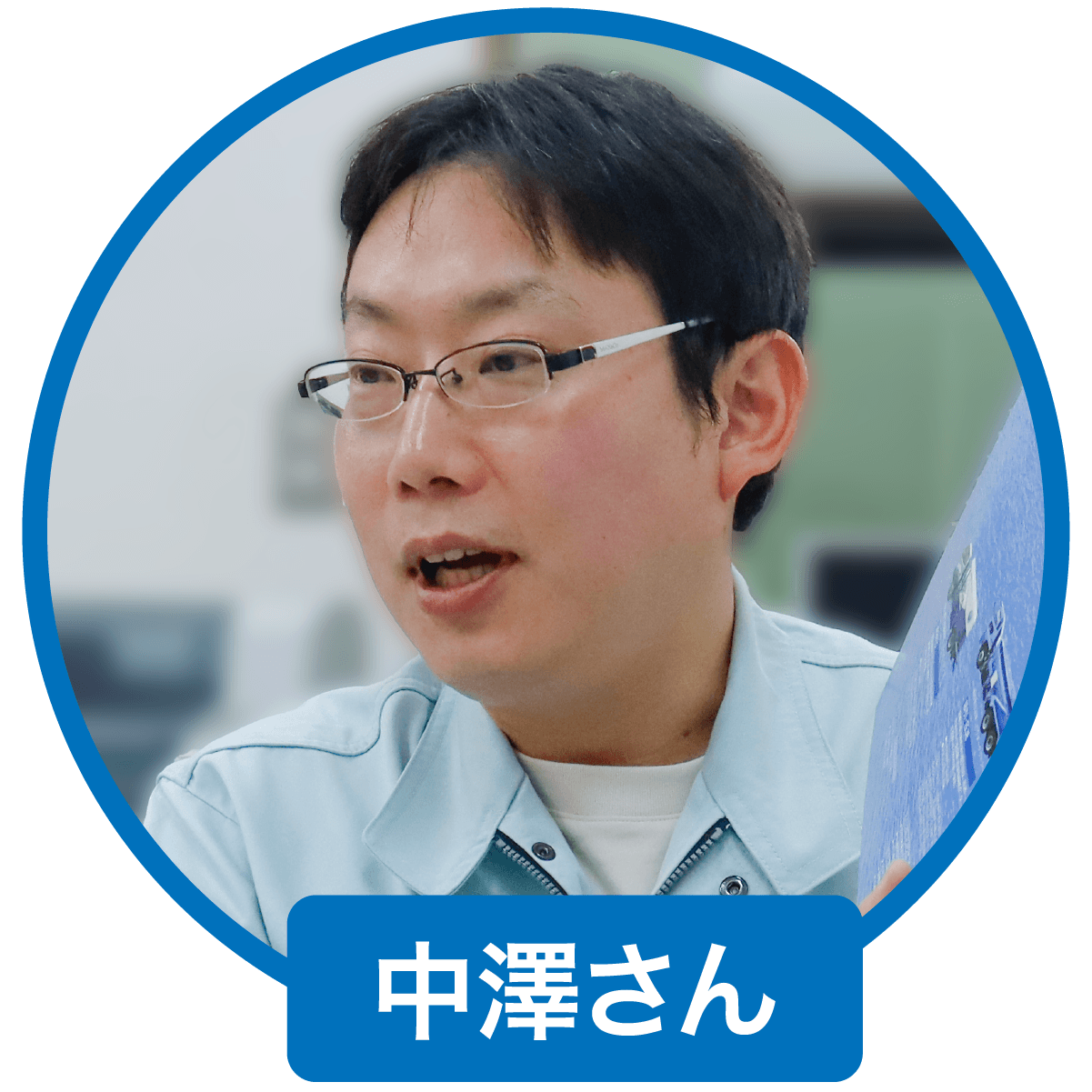
- 当社は「環境整備機器」のメーカーとして、設計・製造・販売をおこなっています。この「環境整備機器」を簡単に言いますと「街をキレイにする車」でして、道路の側溝の清掃、工場や建設現場の廃棄物回収などに使われる強力吸引作業車を主力に、下水道管内を清掃する高圧洗浄車などを製造しております。

-
いわゆる“働く車”ですね。
脱炭素に貢献する製品として注目されている「マイクロ波製品」は、作業車ではありませんね?

-
そうですね。今回お話しする「マイクロ波製品」は作業車ではなく、食品や化粧品などの工場で使われている装置になります。
この装置のベースとなっているのは、当社が長年にわたり開発に取り組んできた強力吸引作業車の真空技術でして、もともとは「運搬コストを下げるために、吸引した汚泥を減量化したい」というお客様の声から生まれたものです。 そこに電子レンジにも利用されているマイクロ波加熱の技術を組み合わせた装置となっています。

- どういったことができる装置ですか?

-
物質は真空状態になると沸点が下がり、中〜低温でも水分を蒸発させることができるようになります。また、マイクロ波を利用すると短時間で加熱することができます。この二つの原理を組み合わせ、乾燥工程の低エネルギー化を実現したのが、この装置です。
効率的、かつ低エネルギーで乾燥工程がおこなえることから、利用するには光熱費のコストがかかるため廃棄処分されるしかなかった残さ(※1)も、低コストで再資源化できるようになりました。そして、食品、化粧品、バイオマス燃料などさまざまな分野における新製品の開発・製造につながっています。
※1 濾過(ろか)したあとなどに残ったかす

- 具体的にどういった製品の工場でマイクロ波製品は導入されていますか?

-
「マイクロ波製品」というのは総称でして、細かくいいますと「乾燥する装置」「成分を濃縮する装置」「成分の抽出をする装置」など目的に応じた装置を展開しております。
装置の実用化に向けて最初に取り組んだのは、2006年、栄養価が高いのに廃棄処分されていた鰹節の煮汁を乾燥によって濃縮させ、ペットフードに利用しようというプロジェクトでした。
さまざまな事情で商品化はされませんでしたが、実用化やその後の発展に向けて手応えのある研究開発だったと思います。 その後、2008年に馬路村農業協同組合様などと共同開発して、ユズの皮から香り高い精油を抽出する「マイクロ波抽出装置」が生まれたのをきっかけに、さまざまな農産物を扱う工場での導入が進みました。
その後、2008年に馬路村農業協同組合様などと共同開発して、ユズの皮から香り高い精油を抽出する「マイクロ波抽出装置」が生まれたのをきっかけに、さまざまな農産物を扱う工場での導入が進みました。
さらに抽出後の残さが家畜や養殖魚の飼料にも活用され、地域の特産品のブランド化にも一役買っています。

-
装置の導入によって未利用資源の活用だけでなく、地域産業も活性化しているんですね。
マイクロ波製品の開発では、どのような苦労がありましたか?

-
理論的には成立しますが、実際に使える装置として実現できるかどうかは未知数でした。そこで、まずは家電販売店で数千円の電子レンジを購入し、分解して基本的な構造を研究するところから始まったんです。
そこから何度もトライアンドエラーを繰り返しました。
ただ、私たちエンジニアにとって「失敗は財産」なんです。数々の失敗から学んだ成果が後々役立ち、特許も取得した装置をいくつも開発することができました。
また、実際に工場などで使っていただくと、作業者の方が操作をしやすいかどうかや、清掃やメンテナンスがしやすいかどうかといった点もブラッシュアップする必要がありました。その点については、もともと当社ではお客様からのご要望に応じて、開発してきましたので、このマイクロ波製品においてもお客様の声をしっかりと聞いてフィードバックし、実用性を高めてまいりました。

- マイクロ波製品は今後どのような可能性があると思いますか?

-
近年オファーを受けて「マイクロ波減圧乾燥技術」を開発しました。この装置によって藻を原料にしたバイオマス燃料の開発が進められています。
当社が開発した装置によって地域の活性化と環境保全につながる新しい製品が続々と生まれてくることは大変嬉しく感じます。
国内初のEV吸引作業車を開発
未来に向けてチャレンジは続く

- 他に環境に配慮した製品はありますか?
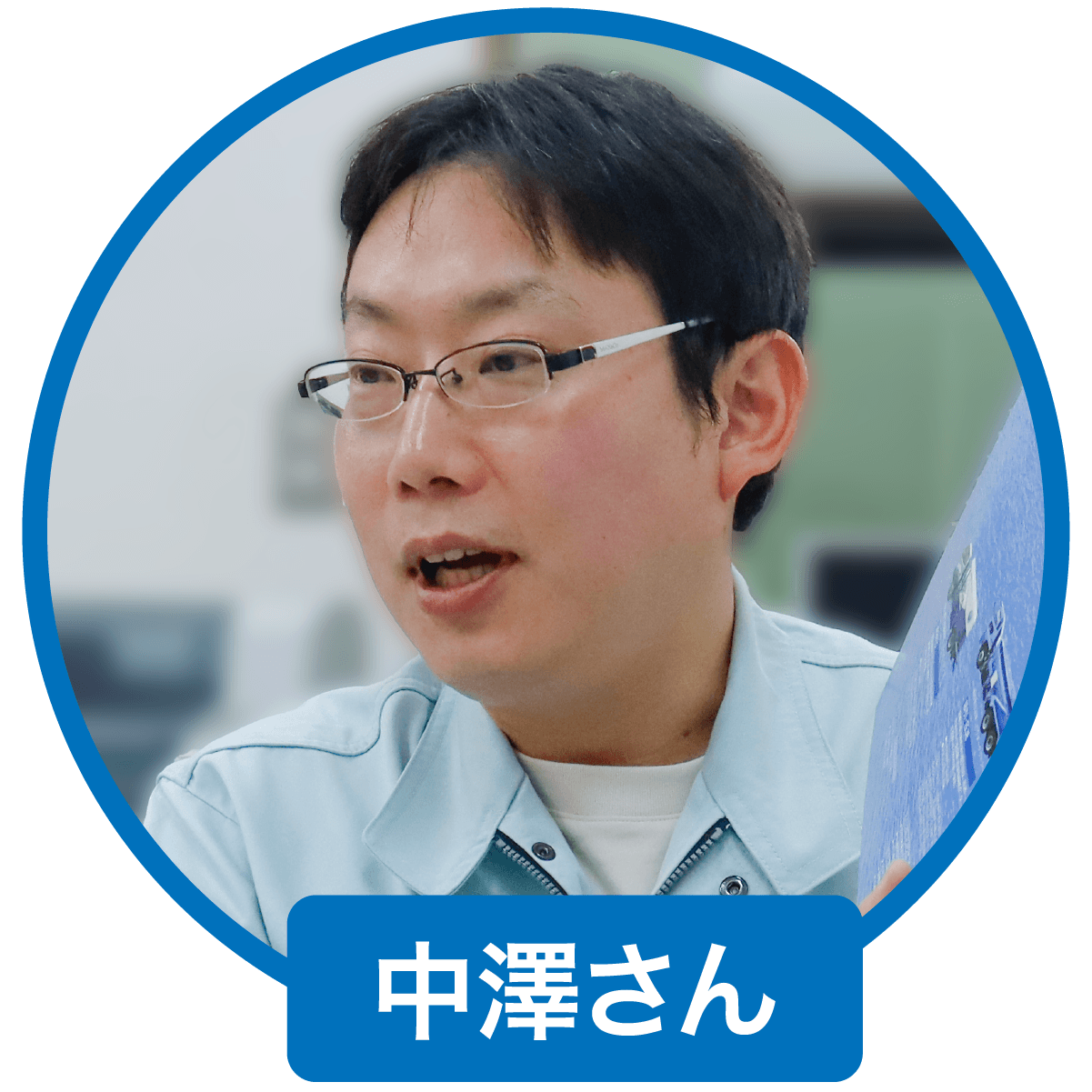
-
SDGsの達成に向けた取組として、われわれの業界ではEV(※2)トラックの開発・発売が活発におこなわれています。当社もEVを活用して環境負荷低減に向けて挑戦をおこなおうという機運が高まりまして、2023年に国内初となるEV吸引作業車を開発しました。

※2 Electric Vehicleの略称で、ガソリンや軽油(ディーゼル)を使用せず、バッテリーに蓄えた電気でモーターを駆動して走る自動車

- 国内初とは素晴らしいですね。開発にあたって苦労されたことを教えてください。
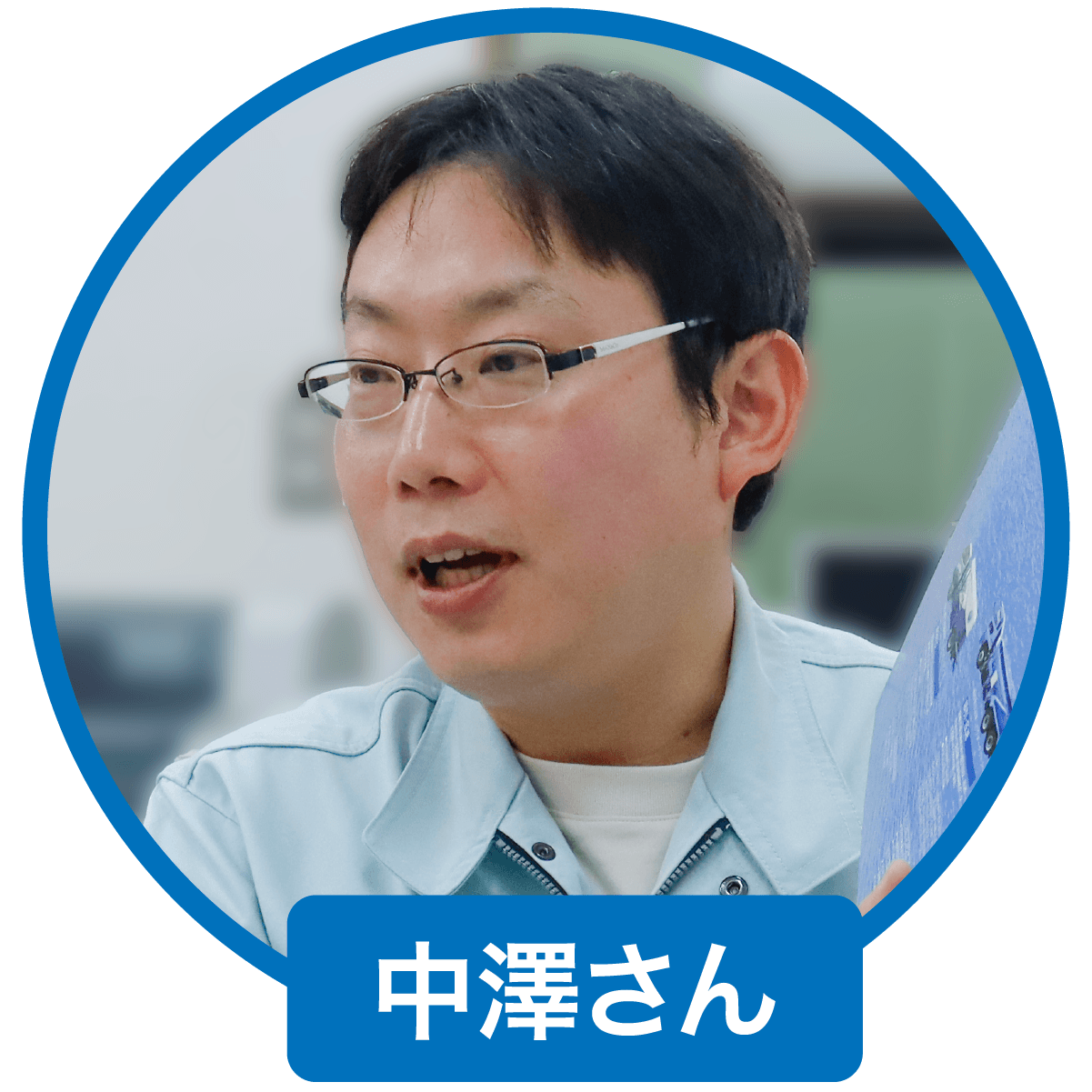
-
それまで当社が製造してきたのは軽油で動くディーゼルトラックでしたので、EVトラックの開発・製造は初めてのことでした。製造にあたっては高い電圧を取り扱う工程がありますので、安全に作業がおこなえるように対策をしなければなりません。
そこで、EV製品を開発されているトラックメーカーに協力を仰ぎ、視察や講習会をおこなって作業員の安全教育からスタートしました。
新しい知識や技術を習得することは簡単ではありませんが、ものづくりにおいて作業の安全性は不可欠ですので、しっかりと理解を深めてから取り組むようにしました。

- 今後、EV吸引作業車を普及していくにあたって、どういった課題がありますか?
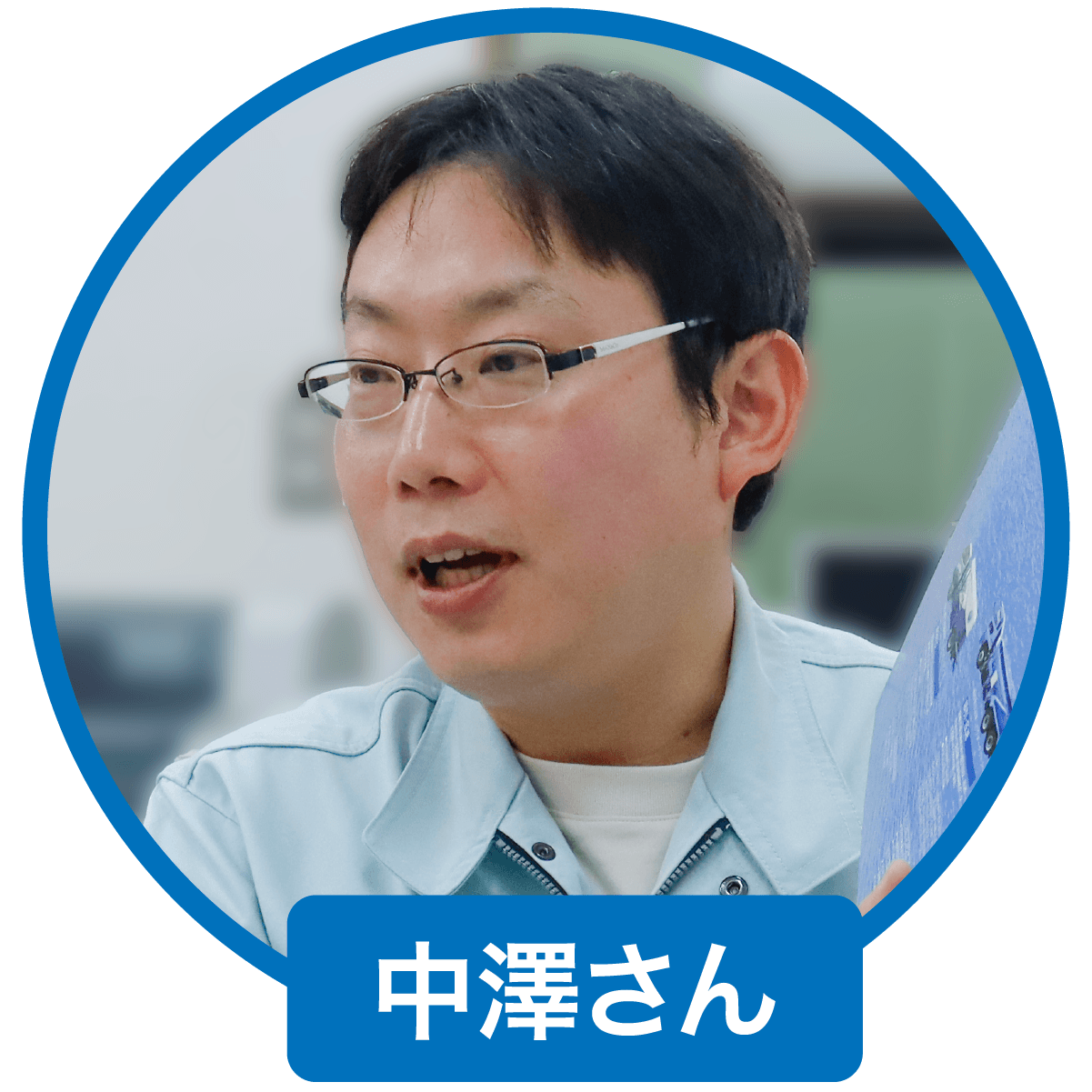
-
実際に街中や現場で働く作業車としては、燃料を補給せずに動く「航続可能距離」と、力強く吸引し続けることのできる「作業可能時間」の両立が課題となっています。
引き続きトラックメーカーと協力し、課題改善と普及に向けてチャレンジを重ねていきたいです。

- では最後に、脱炭素化の実現に向けてどのように取り組んでいきたいか教えてください。
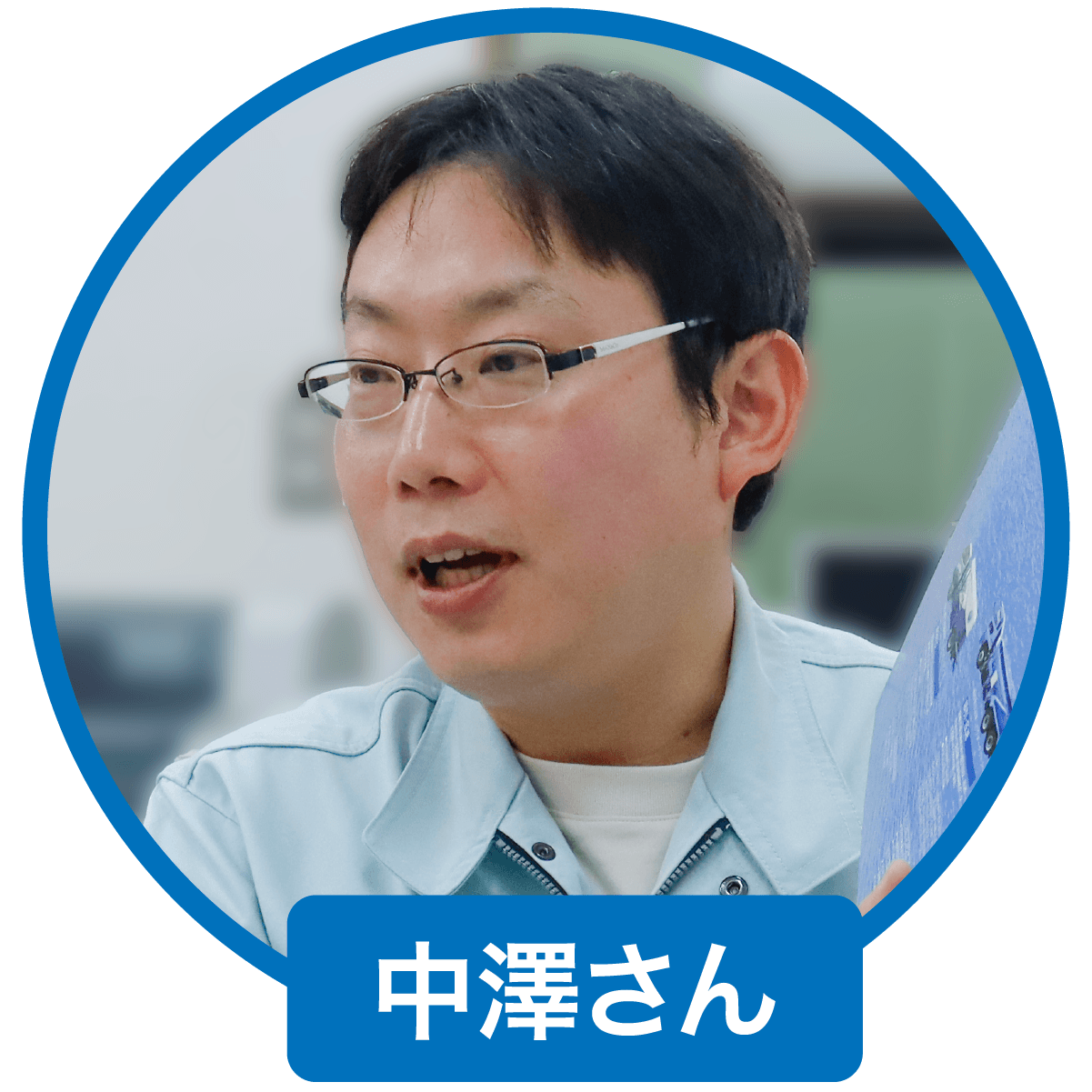
-
当社は「環境整備機器」のメーカーですので、やはり「環境」というテーマが原点にあり続けると考えております。
これからも身近なニーズや声に耳を傾けながら、環境に優しい新しい技術や製品の開発に挑戦し続けていきたいです。
理論や設計の上で成立するアイデアであっても、実用性のある装置としてつくり上げることはとても難しいことだといいます。
エンジニアの皆さんは、途方もない数のトライアンドエラーの繰り返しながら、その中のわずかなヒントを集めて製品化に繋げていくそうです。
環境に優しい商品が増えている背景には、高知のものづくり企業とエンジニアの皆さんの情熱によって完成した素晴らしい装置があることを知り、高知のものづくり魂を誇らしく感じました。
