
お話をしてくれた方
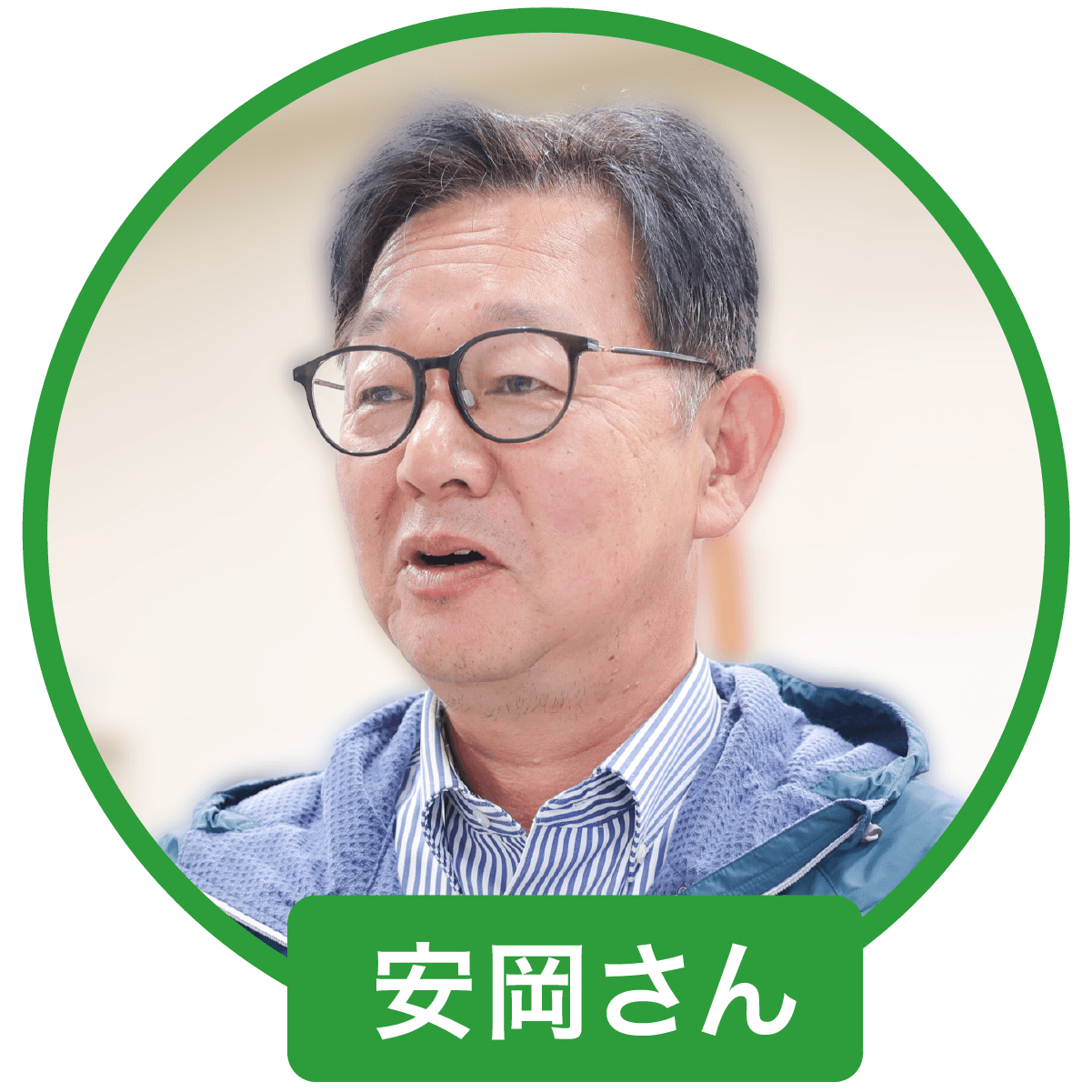
安岡 浩史さん
有限会社安岡重機 代表取締役
素材もエネルギーも地元・高知で「循環」を
今回お話を伺ったのは、「高知県認定環境配慮型事業所」(※1)に認定されている、有限会社安岡重機の代表取締役・安岡浩史さん。
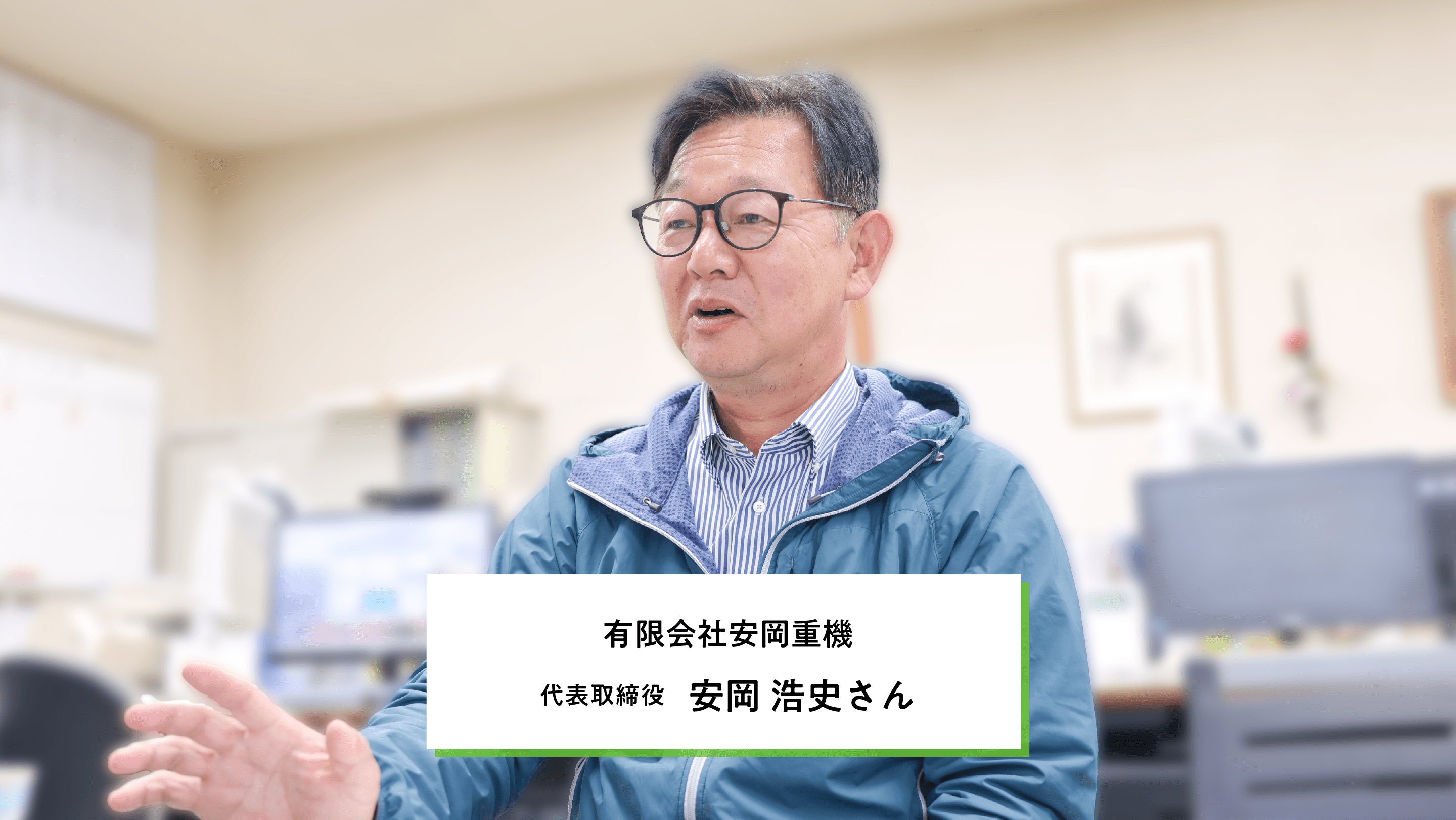
高知県安芸市で、1980年、建設リース業・貨物運送業を主軸とし創設された同社は、2005年に高知県より「環境にやさしい事業所」(※2)に認定され、木質ペレットの開発・製造など、木質バイオマス加工事業を中心に「循環型」の取組を進めてきました。
同社がキーワードとして挙げる「循環」という考え方、木質ペレット開発時の苦労や課題の解決方法、今後の展望などをお聞きしました。
※1 環境に配慮した取組みを積極的に実施し、成果を挙げており、その先進性・アイデア性・技術性等から他事業所における取組みのモデルとなる事業所を高知県は3つの項目に分類し、「環境配慮型事業所」として認定している
※2 「高知県認定環境配慮型事業所」の項目の1つ。事業所から出るごみの発生抑制やリサイクル、省資源、省エネルギー活動を実践し、環境保全活動や環境への負荷を低減する取組みをおこない、著しい成果を挙げている事業所のこと
️未利用材を活用し地産地消の木質ペレットを開発


- 有限会社安岡重機はどのような企業ですか?
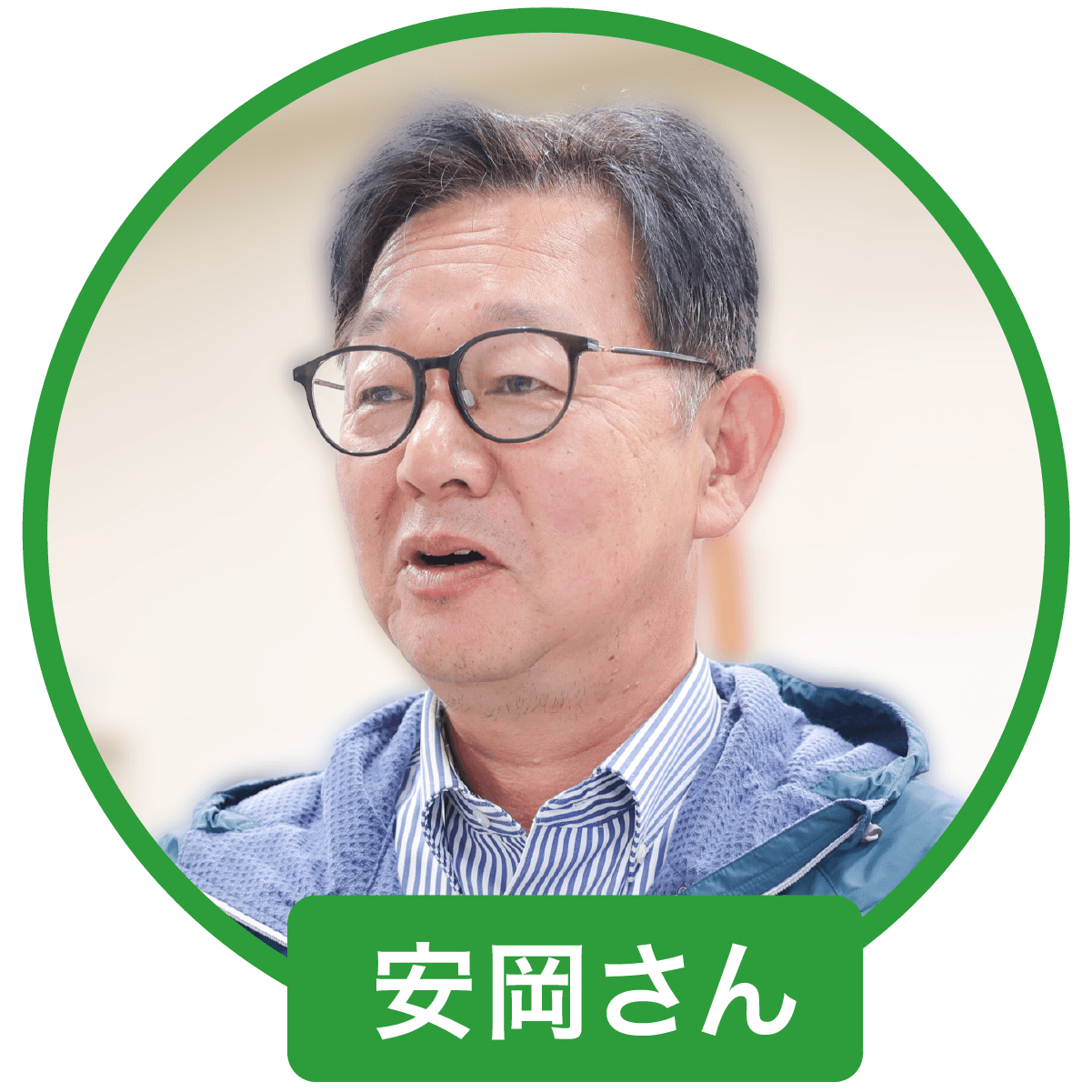
-
当社は、私の父が建設リース業の企業として1980年に創設しました。その他にも貨物運送業や産業廃棄物処分場などの事業を展開しています。
若い頃、私は関東で仕事をしていたのですが、2000年に地元・安芸市に帰ってきて当社の一員になり、2008年に事業を継承しました。そして、当社でこれまでおこなっていた産業廃棄物事業の技術を活用して、木質バイオマス事業(※3)を展開することを検討しました。
キーワードは「循環」です。安芸市の森林率は89%(※4)と高く、安芸市の豊富な資源を最大限に活かしたエネルギーシステムを確立し、地域経済にも貢献できる仕組みを目指しています。
これまでの海外から仕入れていた燃料ではなく、地元・安芸市で生産された燃料を活用し、そこから生み出されるエネルギーを地域に還元し使用してもらうことで、エネルギーを通して、経済が地域内で「循環」できるのではと考えたことがきっかけとなりました。
※3 再生可能な生物由来の有機性資源(化石燃料を除く)のうち、間伐材や造材で生じた木くず・原木・枝葉などの木材からなるバイオマスを利用し、エネルギー供給や資源循環を促進する事業のこと
※4 安芸市役所農林課「安芸市流域森づくり構想を策定しました」より引用

-
地域で生まれた資源を活用する「地産地消」で環境にも優しい取組ですね。
木質ペレット開発までの流れや苦労したことを教えてください。
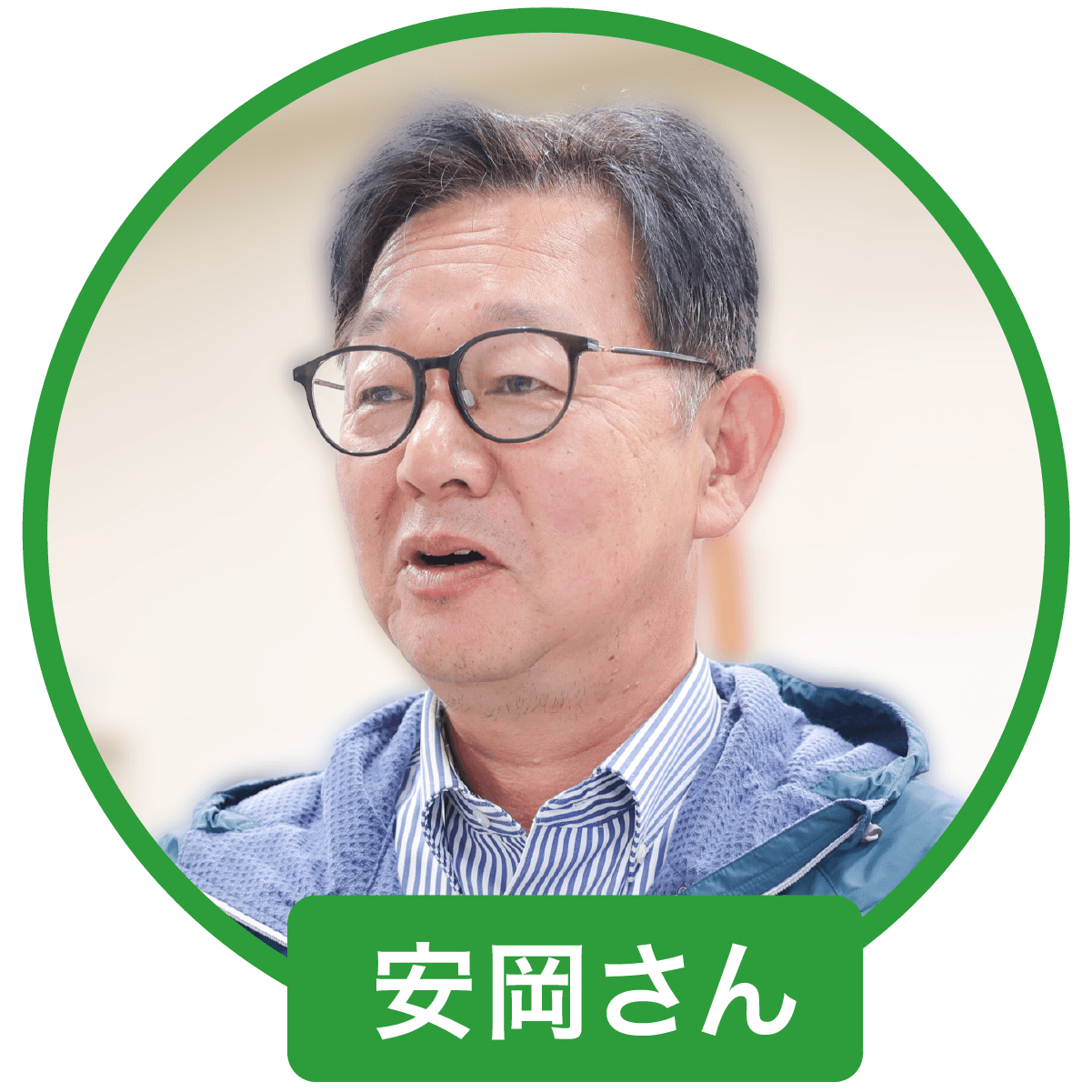
-
木質ペレットは、「未利用材」と言われる本来は捨てられるはずだった木材を活用して製造されています。ヒノキやスギなどの未利用材に「付加価値をつけることはできないか」という思いから、エネルギーとして利用することにしました。
 2009年の開発当初に国の森林整備事業(※5)を活用し、木質バイオマス加工流通施設を建てました。初めての取組だったので、それから3年ほど試行錯誤をしながら進めていました。
2009年の開発当初に国の森林整備事業(※5)を活用し、木質バイオマス加工流通施設を建てました。初めての取組だったので、それから3年ほど試行錯誤をしながら進めていました。
木質ペレットの製造工程ですが、まずは木材を破砕して細かくし、乾燥をさせ、圧縮しながら成形をしていくのですが、その工程の中で特に難しかったのは「乾燥」の部分でした。
※5 高知県の森林が利用期を迎える中、計画的な間伐などの森林整備を推進するため、施業の集約化や低コスト化を図り、森林が健全に育成整備され、公益的機能が高度に発揮されることを目的としてその一部を補助する制度

- 木質ペレットの製造過程で「乾燥」が難しいのはなぜですか?
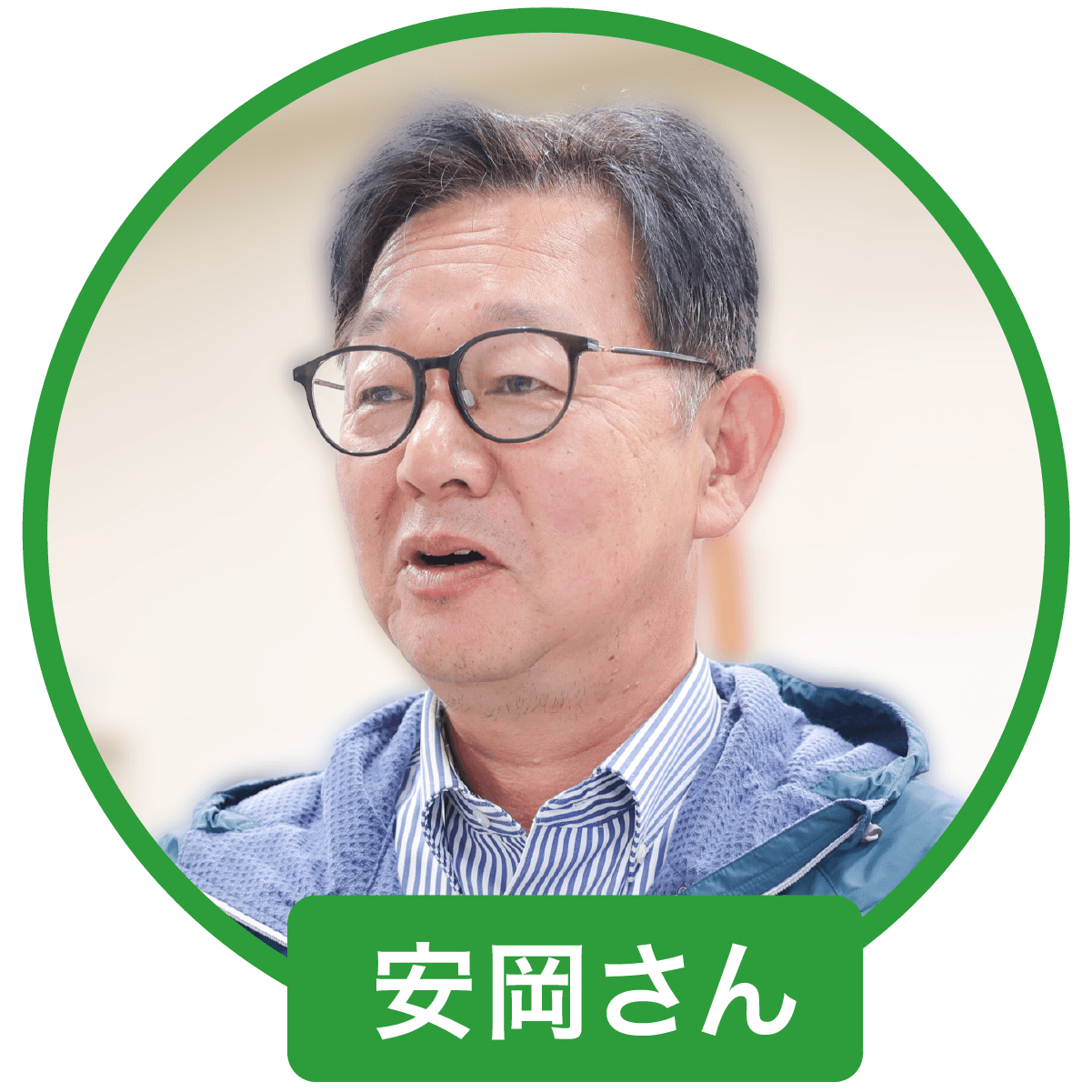
-
元々木材というのは、「生き物」です。生物資源として捉えると、季節(夏・冬)によって含水量が異なるため、木材の乾燥工程では、含水量の管理が重要となります。夏場は含水量が高く、冬場は低いため、それぞれの条件に適した乾燥技術を確立しました。
経験上、季節によって乾燥の度合いが異なるので、当時は乾燥の仕組み自体を解明するのに四苦八苦していました。しかし、効率のいい加温をすることができる乾燥炉の導入支援制度を活用して整備したことで、乾燥の課題が解決されました。
その他にも、乾燥後の成形作業では木の種類によって固まり方が違い、苦労はたくさんありましたが、長年の経験のおかげで現在ではノウハウが培われ、定常的に木質ペレットが製造できるようになりました。 ちなみに、木質ペレットは木そのものが持つ「自然素材の力」でくっついているので、接着剤などの不純物を使用していないため、燃え殻に有害物質はありません。
ちなみに、木質ペレットは木そのものが持つ「自然素材の力」でくっついているので、接着剤などの不純物を使用していないため、燃え殻に有害物質はありません。

-
木という「生き物」だからこその難しさがたくさんあったんですね。
「循環」がキーワードとのことですが、木質ペレットの原材料はどこから来て、どんな場所で使われていますか?
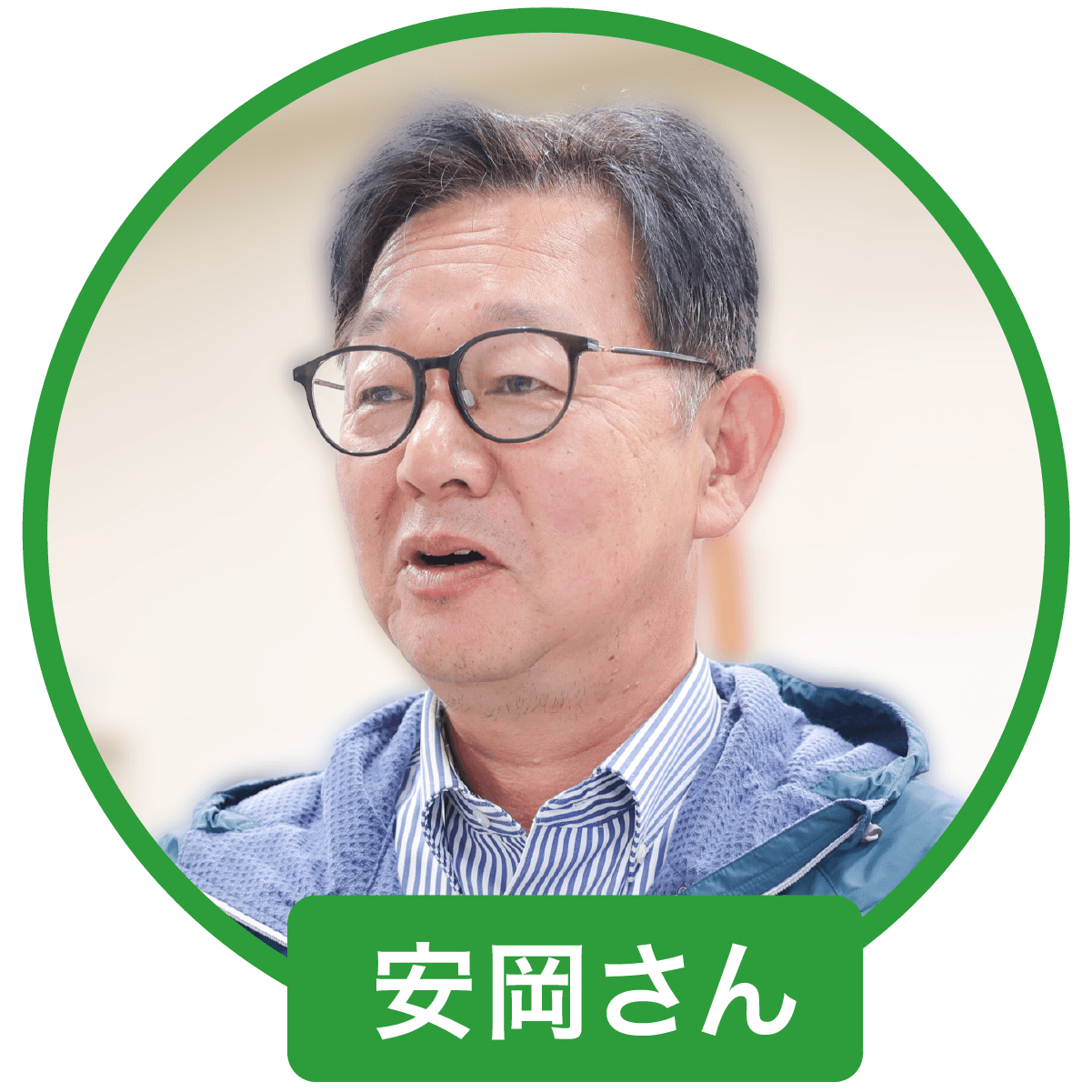
-
木質ペレットの原材料は全て高知県東部を中心とした県産材です。基本は「オール地元」。そして、地元の木材から生まれたエネルギーをまた地元に還しています。安芸市内の農業関係者さんに農業用ボイラーの燃料として使っていただいたり、公共機関の建物の給湯施設などでもご利用いただいています。
製造された燃料を県内ではなく、県外へ持ち運びするとなると、遠ければ遠いほど移動時に車からCO₂(二酸化炭素)が排出されます。そういう環境への影響についても考えて、やっぱり地元で活用していただきたいと思います。

-
農業関係者さんが木質ペレットを燃料として使用したボイラーを活用して野菜や果物を作り、それが私たち消費者の元に届く。そして、公共機関でも使用されているなど、消費者からは見えない部分を木質ペレットが支えてくれていたんですね。
最後になりますが、今後の展望はありますか?
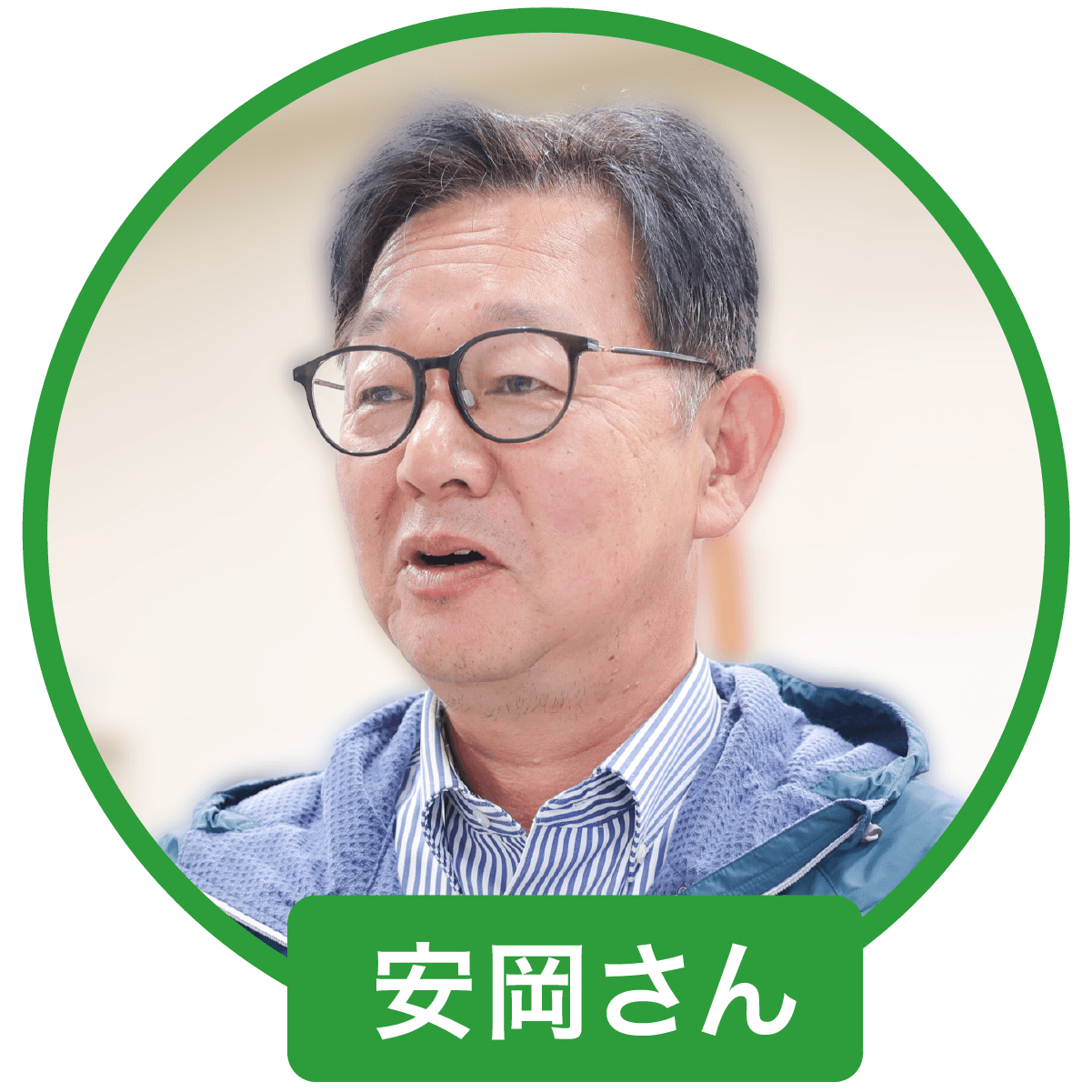
-
今後も「循環」を大切にしていきたいと思っています。エネルギーも循環、素材も循環して、そしてさらに次世代に繋げるということも一番大切なことだと考えています。
安芸市は地元ですが、過疎化が進んで若い世代の人たちが少なくなっています。でも、眠っている良い素材が安芸市にはまだまだたくさんあります。
関係人口(※6)や交流人口(※7)を構築していきながら、多様な人との接点を持つことで、その素材を活用していくアイデアを生み出していけたらと思います。次世代の方々も交えてそういうコミュニティを作って、一緒に新しいものを作っていきたいですね。
※6 移住・観光に来た人口ではない、地域で生活している人からその地域の人々と多様に関わる人々のこと
※7 その地域にはほとんど関わりがない観光やイベントで一時的にその地域に訪れた人々のこと
「地元で作ったものを地元で使う」というシンプルな考えではありますが、持続可能な未来に向けたヒントが詰まっていると思います。実現するまでに多くの困難があったものの、これからも安芸市を元気にするために様々な挑戦を続け、さらに新しいアイデアを生み出そうとする有限会社安岡重機さん。
高知県の地産地消のために、私たちも日々の暮らしでできることを探してみませんか?
