
お話をしてくれた方

田岡 優也さん
tao craft 代表

段松 昌伸さん
tao craft 事業主任
建築用材などとして多く使用される杉やヒノキと違い、シイ、カシ、クヌギなどの広葉樹は製材に手間がかかるため、間伐(※1)などの手入れがなされずに放置されている山がたくさんあります。そんな広葉樹を伐(き)り出して、「素材生産(※2)」と環境にやさしい薪の製造販売を手掛けているtao craftの代表・田岡 優也さん、事業主任・段松 昌伸さんにお話を伺いました。
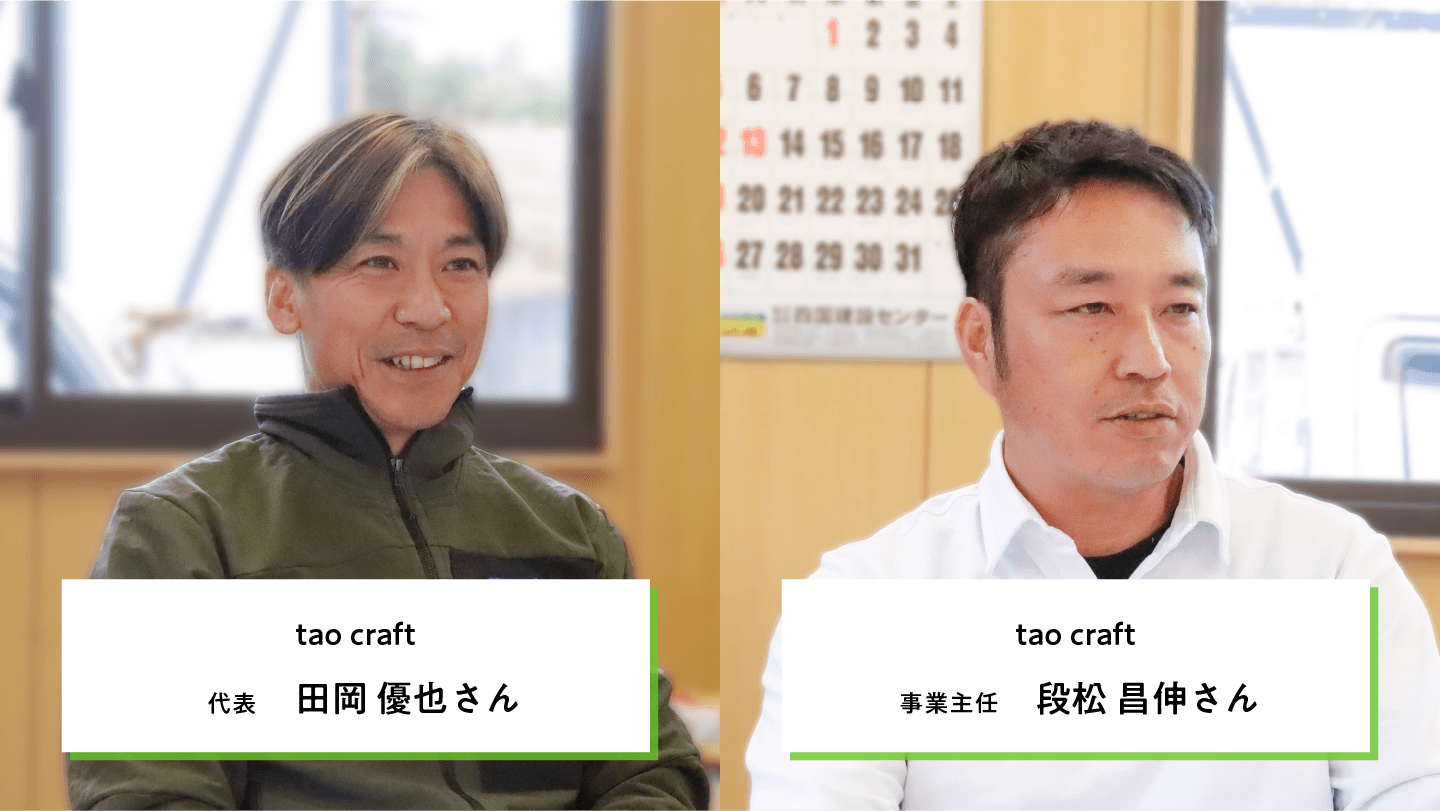
※1 森林の成長に応じて、樹木の一部を伐採し、残った樹木を健全に成長させる作業
※2 国有林に生育する立木(樹木)を伐採して素材(丸太)に加工し、決められた場所に運搬・集積するもの
(林野庁「素材生産請負事業」より引用)
高知県内の森林保全と脱炭素に取り組む会社「tao craft」

- まずは企業概要を教えてください。

- 当社は、森林で育つ木を伐採して丸太に加工する「素材生産」がメイン事業です。国有林、県有林、民間の山主さんが持つ山といった高知県内のさまざまな山の立木(※3)を伐り出して、木材にしています。これは、CO₂(二酸化炭素)を吸収する健全な森づくりにも繋がっています。
※3 地面から生えて育っている樹木のこと
利用用途が限られ放置されることが多い広葉樹に着目


- tao craftを立ち上げた経緯を教えてください。

-
元々、私は建設業で働いていて、父が林業に携わっていました。父から誘いを受けて民間の林業を手がける会社に入社し、4年ほど働いた後、自分でやってみようと起業しました。
そこで、建築用材としてあまり使われない広葉樹に着目し、素材生産ができないかと考えました。

- なぜ広葉樹は建築用材として使われないのですか?

- 杉やヒノキなどの針葉樹とは違い、広葉樹は真っ直ぐに成長しません。真っ直ぐで長さがあり、加工しやすいことが求められる建築用材において、その点で広葉樹はあまり向いていません。そのため需要が限られており、針葉樹のように手入れはされず、育ちっぱなしで放置されている広葉樹がとても多いのが現状です。

- 広葉樹が放置されていると困ることがあるんですか?

-
間伐や伐採がなされないと、木の枝や葉で山が覆われて日光が地面まで届きません。そうすると下草(※4)が生えないので、大雨の際に地盤が緩くなりやすく、災害に繋がる危険も高まるんです。
また、太陽の光が地面まで届き、さまざまな植物が元気に育つ健康な森はCO₂(二酸化炭素)をより多く吸収できますが、手入れされていない森はその機能も低下してしまいます。そのため、本来適度な手入れが必要なんですが、手付かずの山がほとんどです。
私たちが伐り出すことが山の手入れに繋がり、災害も少なくなり、森のCO₂(二酸化炭素)吸収力も高まると考えています。
植林しないと生えてこない針葉樹と違い、広葉樹は自然に芽吹いてくるので、放置するのではなく針葉樹と同様に定期的な観察や手入れをしていくことが大事だと考えています。
※4 森林の低い位置に生える草や低木のこと

-
木々の適切な管理が脱炭素だけではなく、減災にも繋がっているのですね。
では、作業の過程などを教えてください。

-
簡単にいうと、まず伐倒し、その木を作業道まで集材します。そして枝払いをし、決められた長さに切る「玉切り」をおこないます。用途に合わせ、チェーンソーで一つひとつ丸太にするまでが、山での作業です。薪に使用する丸太は、そこから会社へ持ち帰って、水分がなくなるまで自然乾燥させます。

1本1本手作業で磨く薪の製造と販売も手がける

- 素材生産だけでなく、薪も製造しているんですか?

- はい。元々は株式会社相愛が手がけていた薪事業ですが、2023年に引き継いで薪の製造から販売までおこなっています。薪を使用することは、石油などの化石燃料の代わりになるので、環境にやさしく脱炭素にも貢献できます。

- 薪を燃やしてもCO₂(二酸化炭素)は排出されると思うんですが、どのように脱炭素に繋がるのでしょうか?

- 木は成長する過程で大気中のCO₂(二酸化炭素)を吸収します。その木を燃やすと、確かにCO₂(二酸化炭素)は排出されますが、それは木が成長する際に吸収した量と同じなので、全体としてプラスマイナスゼロになります。これを「カーボンニュートラル」と言います。そのため、薪は「環境にやさしい燃料」なんです。

- 広葉樹を伐採することで森林の健全化にも繋がるし、薪を活用することはカーボンニュートラルなんですね。tao craftさんの薪は、一般的な薪との違いはありますか?

-
私たちの薪は広葉樹を使用しているので、一般的な針葉樹の薪よりも火の保ちがいいことです。また、煙が少ないことも特徴です。これは特に乾燥に気を使っていて、半年から1年ほどかけて含水率(※5)を20%以下まで乾かしています。年間約300tの木を伐り出しますが、乾燥後には約200tになります。つまり、約100tは水分なんです。それくらい木には水分が含まれています。水分が多い薪は、着火の際に煙が多く出る原因にもなるので、そういったところをこだわっています。
また、1本1本手作業で薪を磨き、カビや虫痕などをなるべく取り除くようにしています。こういった部分で、高品質な薪になるよう努めています。
※5 木材の重量に対して含まれる水分量の割合のことで、木材を乾燥させる際の基準の1つになっている

-
乾燥に清掃と薪を作るのに手間も時間もかかるのですね。
事業を展開する中で苦労したことはありますか?

-
特に大変だったという記憶はないです。むしろ林業をしている人が少ないので、「木を伐ってほしい」という声が多く、広葉樹の伐採をすると「ありがとう」と言ってもらえることがやりがいにも繋がっています。
一緒に働く仲間も、「手作業が多く大変だけど楽しいし、地域貢献と環境保全に繋がっていることが誇り」と思ってくれています。また、木を伐り出して感謝されると同時に、高知県内で当社の薪を使ってくれている鰹節屋さんやピザ屋さん、キャンプ場などプロの方から喜びの声が届いたり、薪ストーブを利用される方からも火力や火の保ちについて誉めていただけることがモチベーションにも繋がっています。
山の整備と植樹、雇用促進で循環型の事業を展開

- 木を伐り出した後はそのままにして、また広葉樹が育つのを待つのですか?

- いいえ。伐った後は針葉樹を植えます。建築用材になる針葉樹は自然には生えてこないので、私たちの子どもや孫の世代のためにも、植樹活動もおこないます。広葉樹と針葉樹がバランスよく育つ、健全な森づくりを目指しています。

-
未来に繋がる素敵な取組ですね。
今後の展望はありますか?

-
協働してくれている福祉事業者や仲間を増やして、雇用の場所も増やしていけたらと考えています。薪の箱詰めや磨きなど、障がいのある方と一緒にできる工程もあるので、福祉事業者と提携することで、就労支援や地域貢献にも繋げられると思います。手作業でおこなう工程が多いので、一緒にやってくださる方が多いと、私たちも助かります。
また、薪を作っていると木屑や樹皮も大量に出るので、それらを薪を乾燥させる際の熱源に利用することで、クリーンエネルギーとしての活用ができないかと検討しています。 森林の整備で高知の自然とCO₂(二酸化炭素)を循環させ、植樹により未来の森を守り、雇用を増やして社会貢献をしていく、これらの活動が一つひとつ繋がって森林率日本一の高知県から未来を作っていけたらいいなと思います。
森林の整備で高知の自然とCO₂(二酸化炭素)を循環させ、植樹により未来の森を守り、雇用を増やして社会貢献をしていく、これらの活動が一つひとつ繋がって森林率日本一の高知県から未来を作っていけたらいいなと思います。
放置林の整備や間伐が、CO₂(二酸化炭素)の吸収に欠かせない森林を守るだけでなく、木材として加工・販売することで有効活用に繋げ、その薪を使うことにより化石燃料の消費削減にも繋がっているんだと感じました。
tao craftの「tao」は、中国哲学や道教の教えからくる「道」に由来するそうです。
高知県の未来と地球環境を守る「道」づくりに貢献している素敵な企業に出会いました。
