
お話をしてくれた方
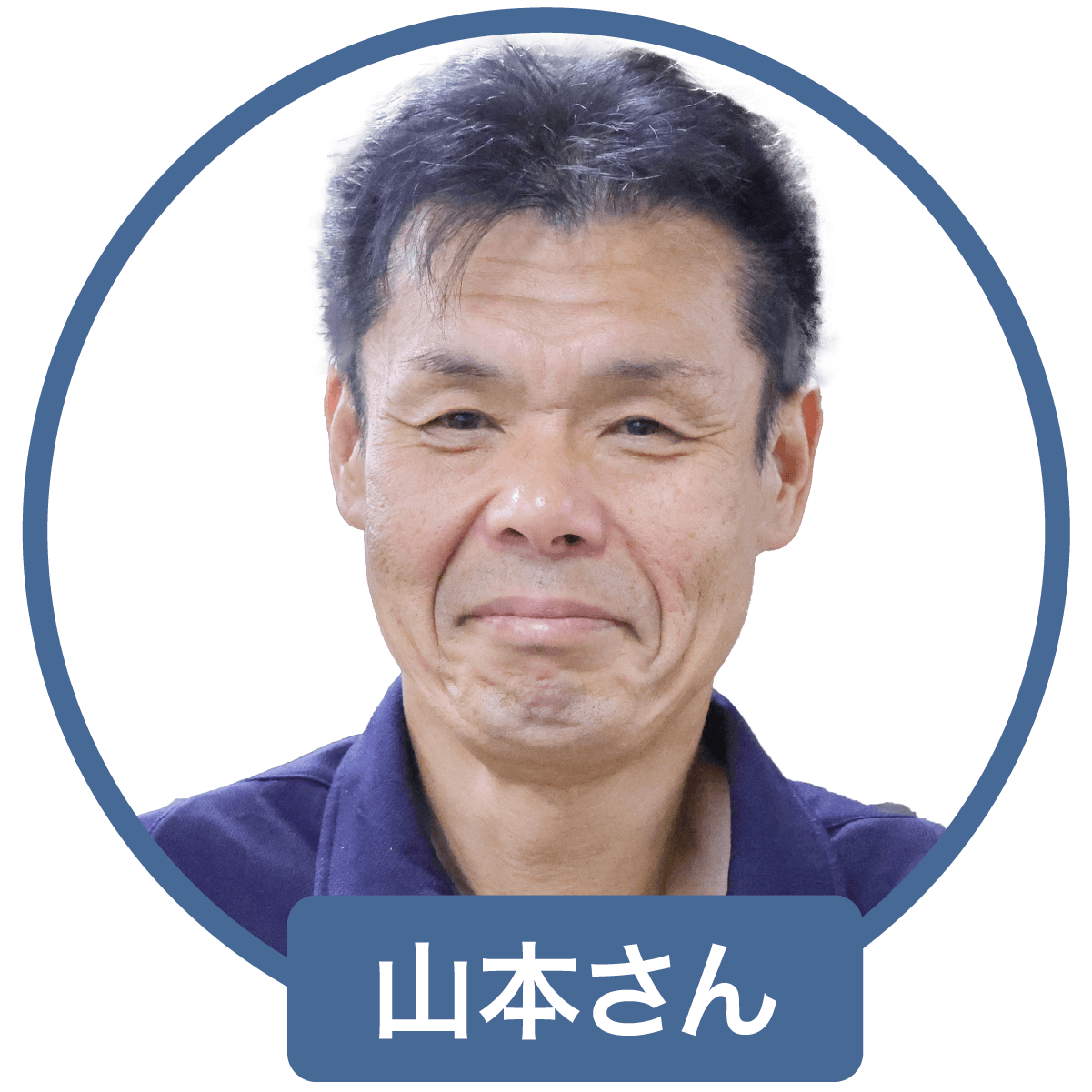
山本 正幸さん
有限会社山本かまぼこ店 代表取締役
漁師町・室戸で愛されてきた味を守り続ける老舗のかまぼこ店
魚のすり身を原材料につくる「かまぼこ」や「てんぷら(さつま揚げ)」は、ぷりっと弾力のある食感と噛むほどに魚のうま味が楽しめる国民食です。 特に室戸市では、遠洋漁業に向かう漁師達が船へ大量に積みこみ、毎食の楽しみにしていたといいます。
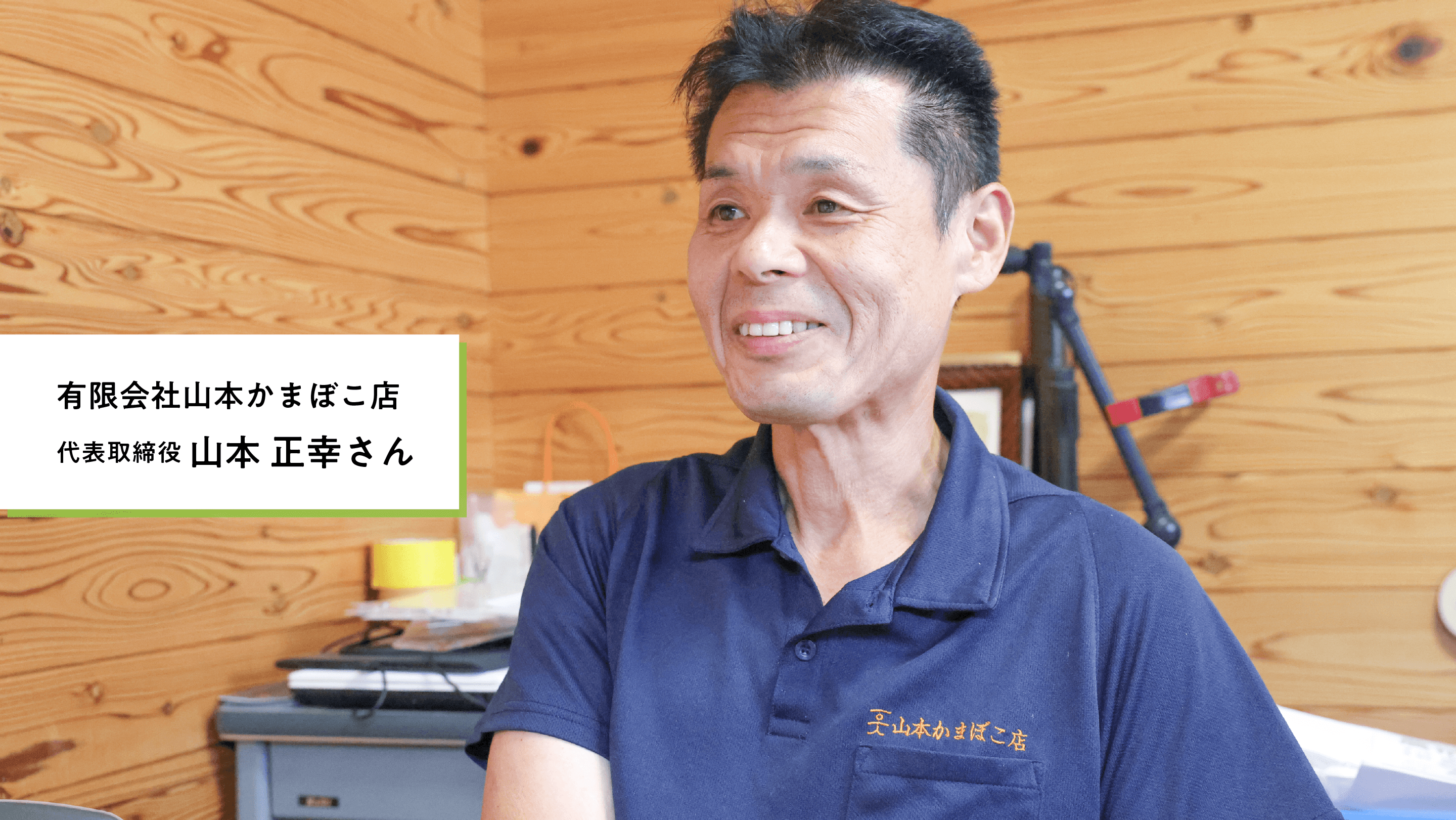
そんな室戸の漁師達の“ソウルフード”を1938年の創業以来、つくり続けているのが「有限会社山本かまぼこ店」です。今回は三代目となる代表取締役・山本 正幸さんに脱炭素を目指した取組についてお話を伺います。
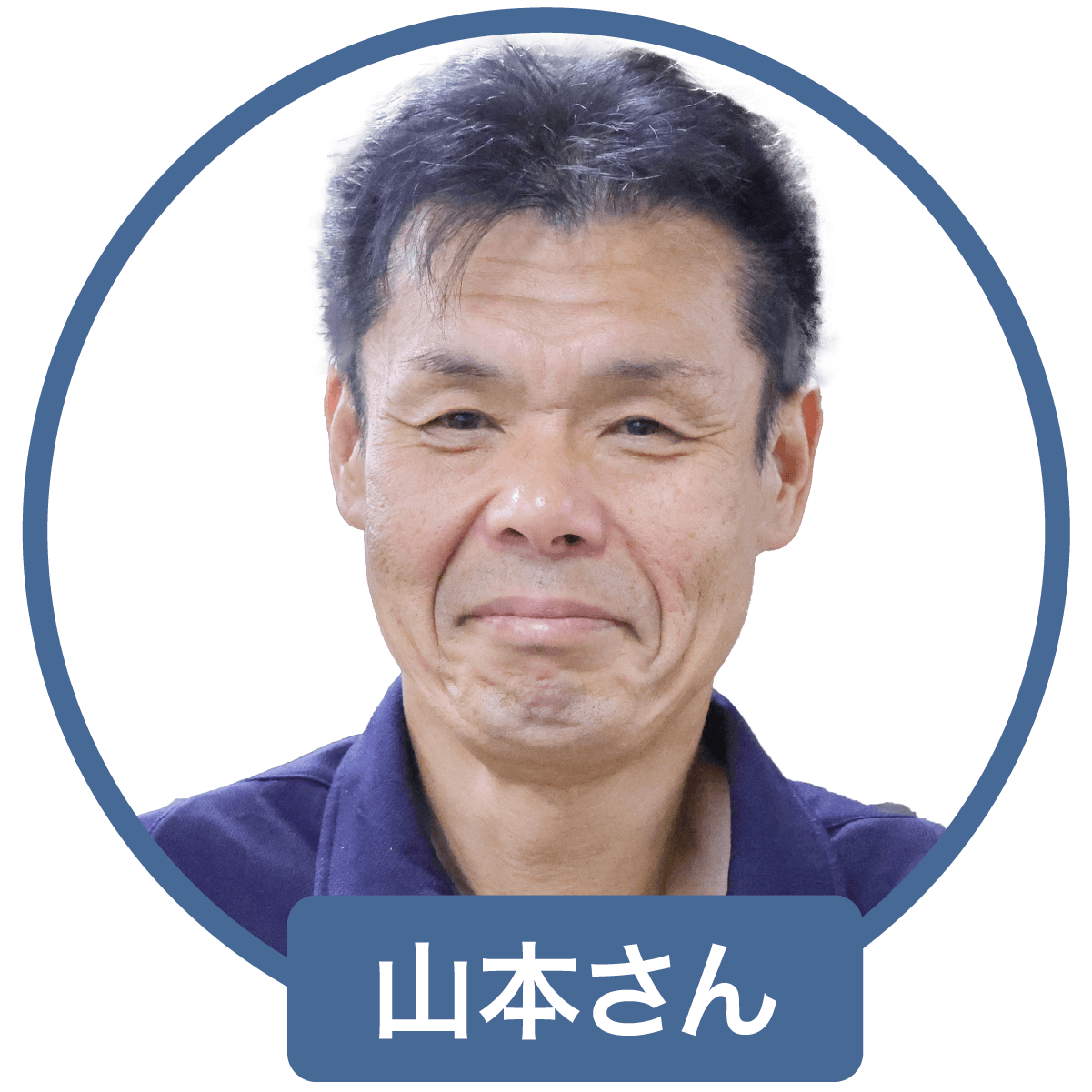
- 当社の工場内ではさまざまな製造機械が稼働しており、焼く・蒸す・揚げるといった工程ではエネルギーも必要です。そこで再生可能エネルギー(※1)の導入や、省エネ設備の導入を進めて、エネルギー消費の削減に取り組んでいます。 とはいっても、当社は小さな工場ですし、日々の製品づくりと並行して、設備の入れ替えをおこなわなければなりませんので、一気に入れ替えることは難しいのが現実です。部分的にはなりますが、それでもアクションを積み重ねていくことが大事だと考えています。
※1 石油や石炭といった化石燃料とは異なり、自然の活動によってエネルギー源が絶えず再生、供給され、利用時にCO₂(二酸化炭素)が増加しないエネルギー源


- 他にどんな取組をしていますか?
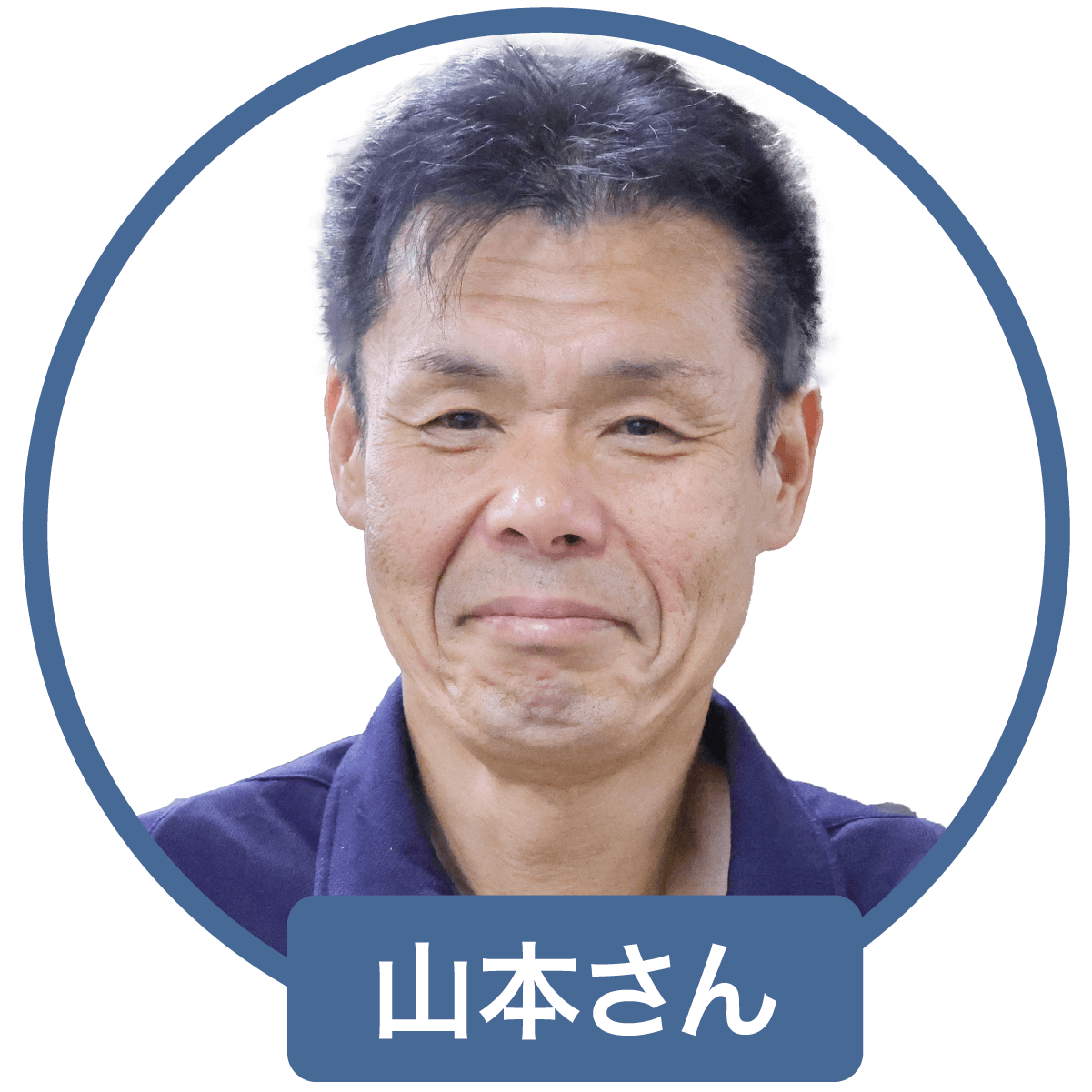
-
サプライチェーン、つまり、原料調達からはじまり、製造→配送→販売→消費といった製品がお客様に届くまでの一連の流れの見直しをおこないました。
そこでまずは、地元の材料を積極的に使うことに取り組みました。例えば、魚のシイラや、おでん製品用の大根やにんじんなどです。遠くの産地の材料を使う場合、輸送の際に多くのCO₂(二酸化炭素)が排出されますが、近くでとれた材料を使えばその分排出量が低減できます。さらに、地元の材料を使うことで地産地消にも繋がっています。

-
製品を作るための材料の移動から脱炭素の取組は始まっているんですね。
地域と環境に優しい一石二鳥な取組ですね。
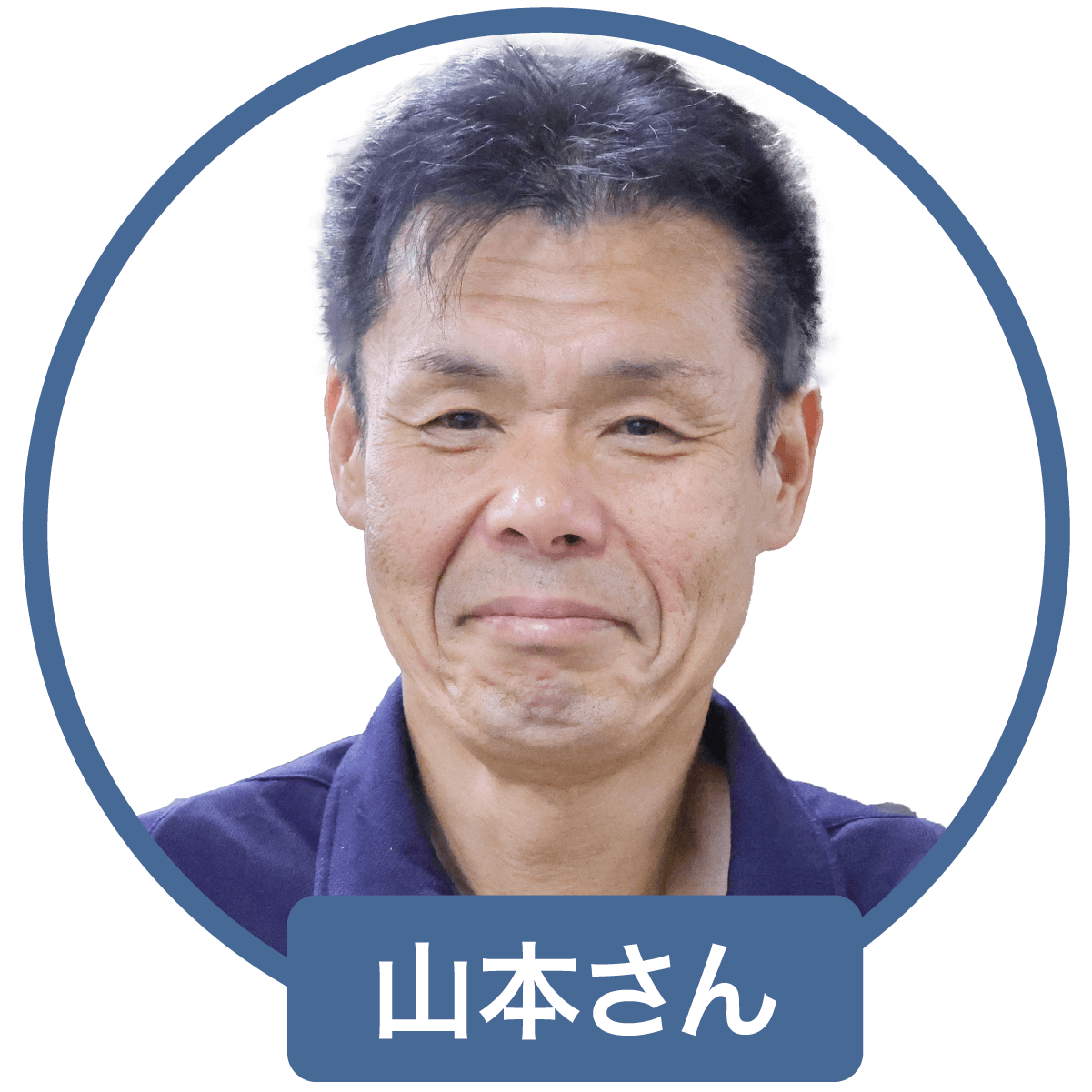
- そして、製品自体の環境負荷の低減にも取り組んでいます。 例えば、環境に負荷の少ない包装材に変更したり、冷凍保存が可能なロングライフ商品や常温保存が可能な商品を開発しています。


- かまぼこやてんぷらは、一般的には冷蔵保存で賞味期限は1週間程度といわれていますが、どれくらい保ちますか?
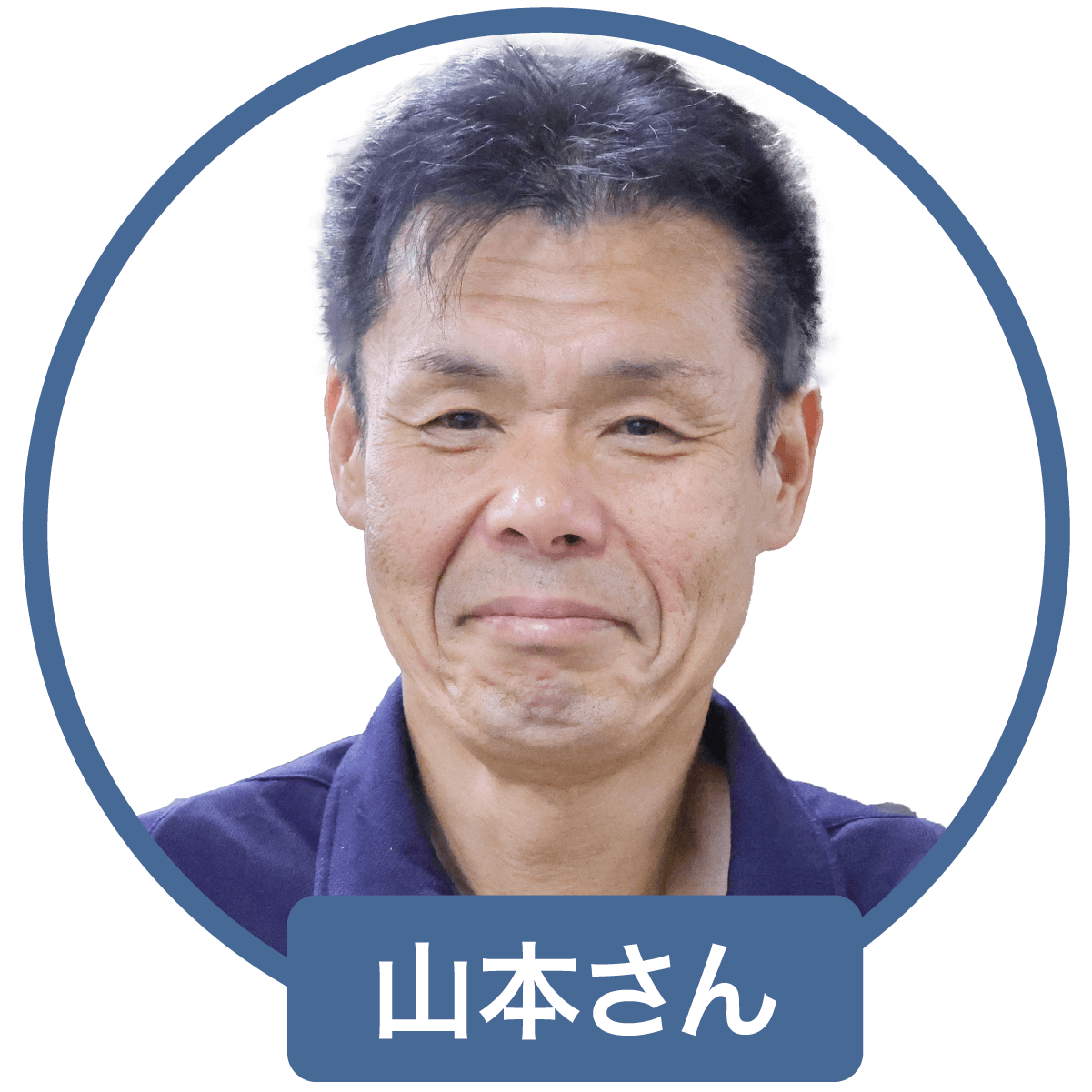
-
ロングライフ商品は冷凍保存をすれば365日、常温保存商品は常温で100日の賞味期限となります。
賞味期限を長くすることは食品ロスの削減にも繋がりますので、そこに大きな意義を感じて開発をおこないました。環境に配慮した商品開発や取組を続けていたところ、同じように考えて取り組んでいる宿泊施設様の目に留まって新たなご縁が生まれたり、環境意識の高い消費者の方が数ある商品の中から当社商品を選んでいただくきっかけとなるなど、ビジネスにおいてもメリットが多いと感じています。
ヒントは原点にあり!冷凍保存してもおいしい商品で食品ロスを削減


- 開発するにあたってヒントになったものはありますか?
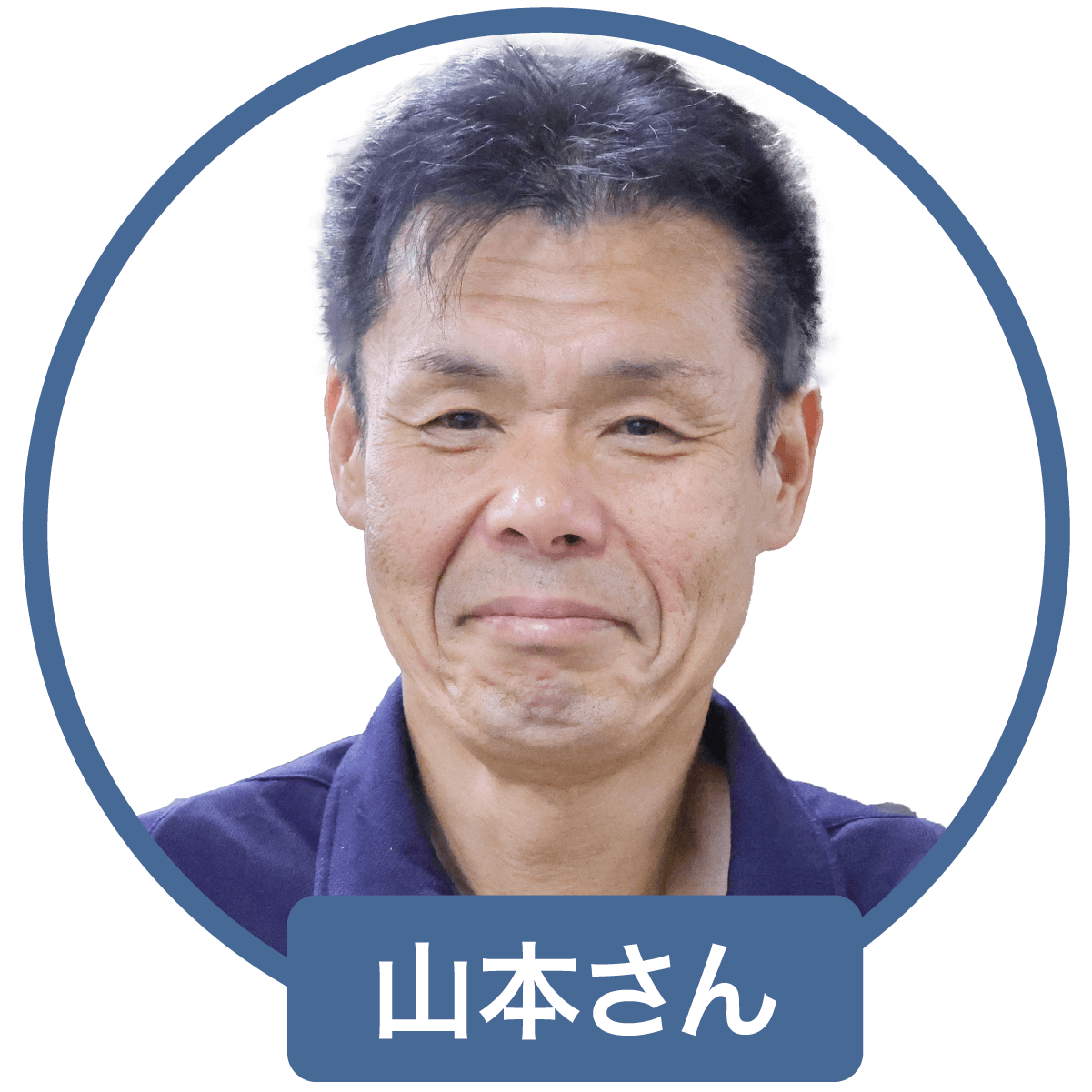
-
ヒントとなるものは、私たちの“原点”にありました。
もともと当社のかまぼこやてんぷらは、漁船内の冷凍庫に積みこまれて、長い時間、船上で寝食する漁師さん達の食材として親しまれていました。手前味噌になりますが、魚のプロである漁師さんから「冷凍保存してもおいしい」とお墨付きをいただいていたのです。
時代の流れともに量販店での販売・ご家庭での消費がメインとなり、冷凍から冷蔵へと保存方法が変わっていったことで、原材料や製法も変化していましたが、原点回帰することで「冷凍保存してもおいしい」商品を、再び世に出せることになったんです。

- ドラマチックな展開ですね。
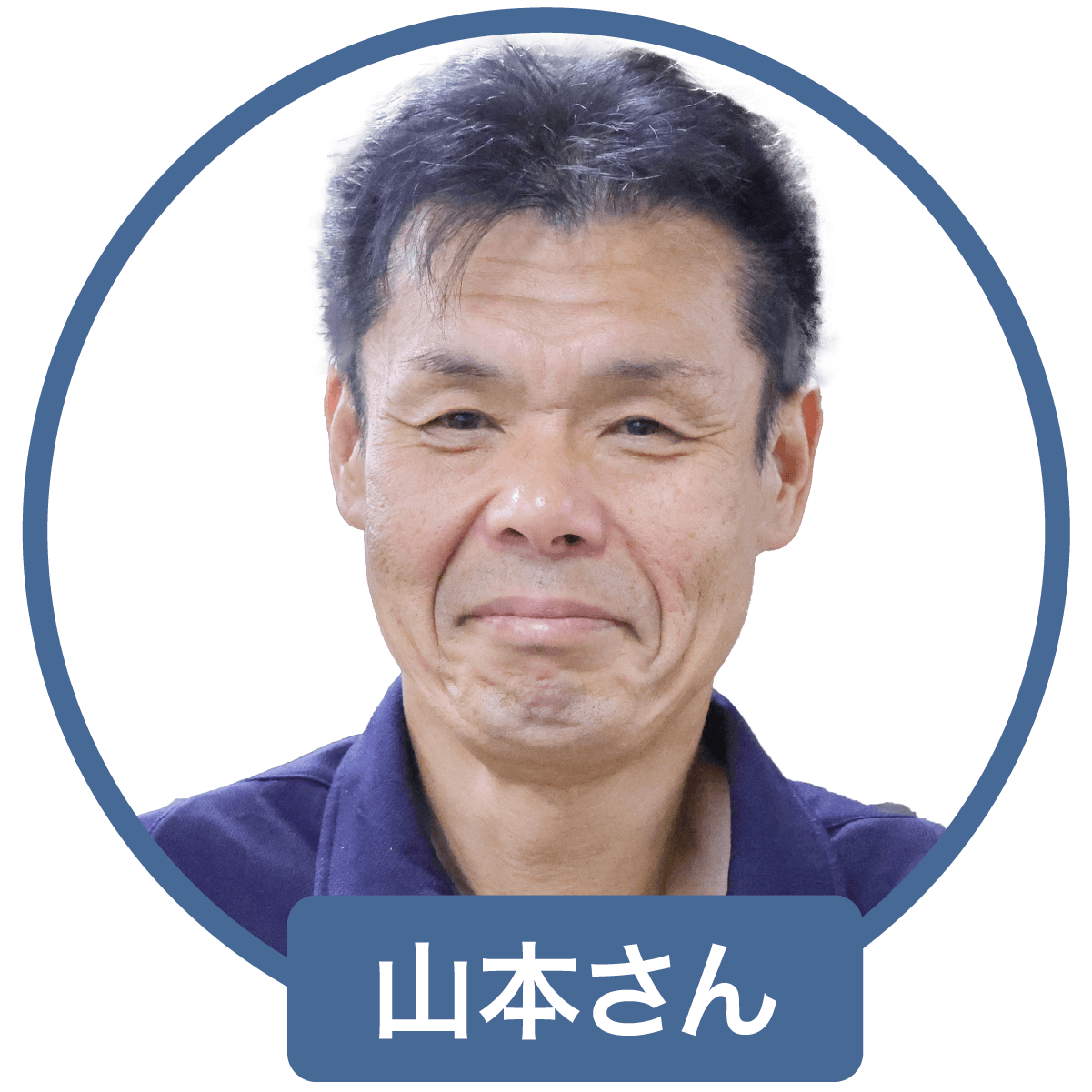
-
当社のような伝統産業の会社が脱炭素をはじめとする環境に配慮した取組を始めようとなると、新しい設備や大きな変化が必要になるイメージがあり、高いハードルを感じる経営者の方も多いと思います。
実際に当社も設備の入れ替えを計画しておりますが、導入資金の問題や、入れ替え期間中に工場の稼働をどうするかなど、さまざまな課題があります。経営者としては見て見ぬふりをする方がラクかもしれません。
しかし、自社の事業を将来的にも持続可能なものにしていくためには、目を逸らしてはいけないと考えています。当社のように原点にヒントがある場合もありますし、周囲の方々がヒントをくださることもあります。「視野を広げて、まずは出来ることからやってみる!」それが大事だと感じます。

-
伝統産業だからこそ変化していくことの難しさがあるんですね。でも、伝統産業には高知の特色や魅力が詰まっているので、未来に残っていってほしいと思います。
まずは、できることから一歩一歩着実に取り組んでいくことが大事ですね。
では、最後に、今後はどのようなことに取り組んでいきたいですか?
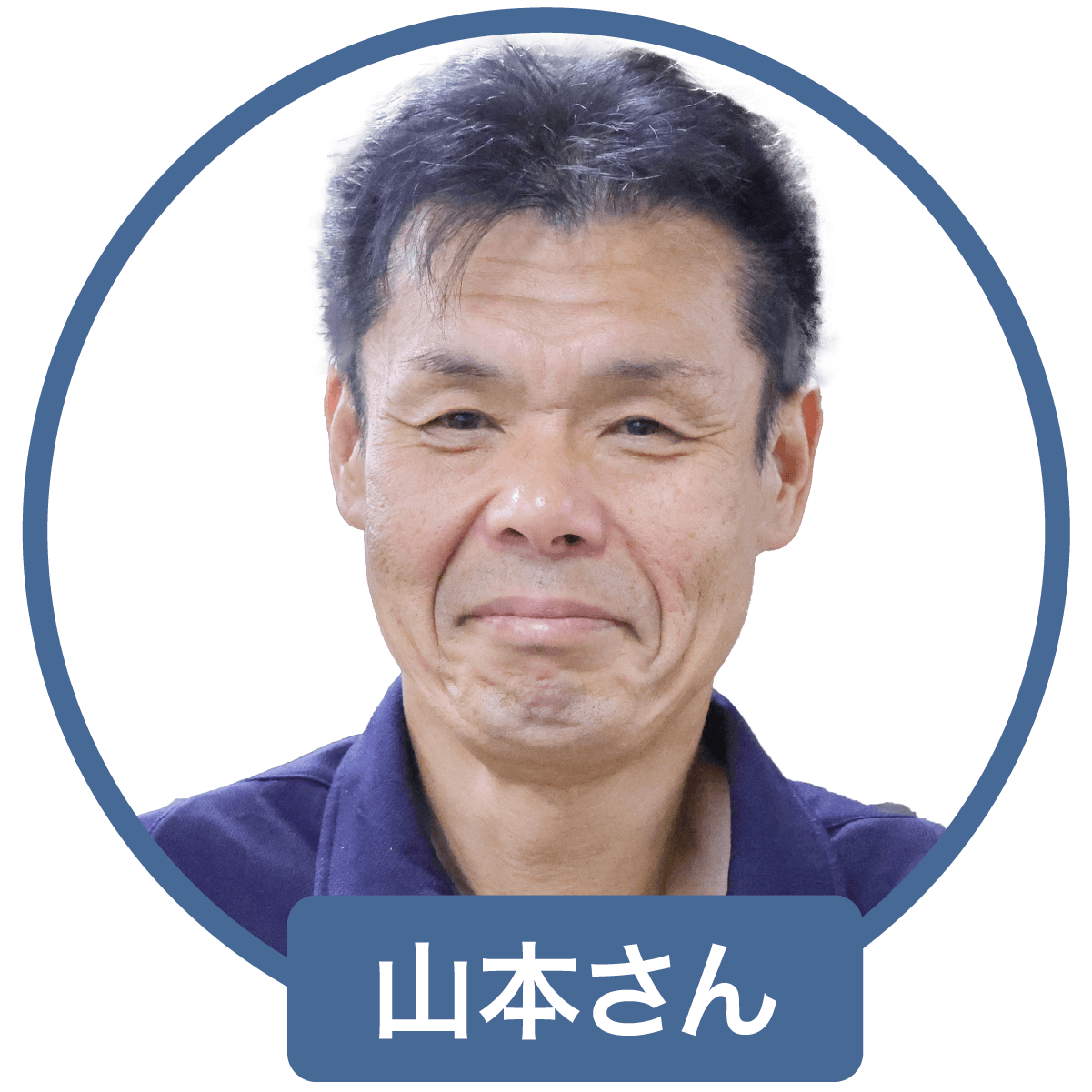
-
環境に配慮した設備を導入し、地域の子ども達にも見学してもらえるような新工場の建設を目指しています。
決して簡単な目標ではありませんが、私は「田舎だからできない」ではなく、「室戸からでもチャレンジできる!」という証明をしていきたいんです。
もちろん自分一人ではできません。お客様、周囲のみなさま、従業員、家族など私をサポートしてくれる人がいるから、目標を持てます。みなさんと気持ちを一つにしながら、いま自分たちにできることから取り組んで行きたいです。
今回お話してくださった山本さんは、休日に小型バイクに乗って山道を走るのがご趣味で、自然を感じたり、気になるものがあれば停まって眺めたりしているそうです。そうした時間がご自身の環境意識に繋がっているのかもしれません。
